
待望のアメリカ旅行に行ってきました。私の中で憧れのアメリカというのは、サンフランシスコやニューヨークといった華やかな感じのイメージではなく、なぜだか開拓時代のアメリカなのです。
私が初めて憧れたアメリカは1970年代に書かれた『大草原の小さな家』の舞台であるミネソタの草原、ブッシュに実るベリー類、それらで作るお菓子やスープ。丸太小屋に飾られた大きなパッチワーク、手作りの家具でした。
初めての出会いは本だったのかテレビだったのか、今となっては定かではありませんが、我が家の子育て時代はかなり影響されていたのは確かです。トールペインティングまで習いましたから。
今回の目的地は、息子の留学先であるテネシー州のナッシュビルという街です。ここはプレスリーを輩出したことでも有名な音楽の街で、最盛期にはカントリーのレコードの90%がこの町のレコードスタジオで録音されたようです。この街のダウンタウンは夕刻ともなれば街中のライブハウスから大音響で音楽が流れ、道という道が人で溢れます。私はギターやバンジョーのカントリーミュージックを期待していたのですが、相当賑やかで、私には心地良いとは感じられませんでした。なにか別世界に迷い込んだ感じで、息子の後ろをきょろきょろしながらも懸命について歩きました。

アメリカはマックやケンタッキーで溢れていませんでした
アメリカに行く前に息子から「僕の住んでいるところにはマックはないよ」「ランチはジップロックにブロッコリーやコーンを入れて行って食べてる人がいる」「意外に食費が高いから自分で作っている」等と聞いていたので、なんだか自分の想像とは違うらしいと感じながら出かけました。
今回アメリカに行って、しっかり見て体験してこようと思ったのは、米国の子供の3分の1以上、また成人の3分の2以上が過体重や肥満だということですから、私の勝手なアメリカの食生活像は、知識階級は食事も運動もきちんと律した生活をしていて、生活習慣病の予防ができている。しかし貧しい人たちや知識が乏しい人たちがファーストフード等を食べ続けて太っているのではないか? 本当はどうなのだろうか?
アメリカ人は、日本人のように少しの魚介類と木の実、雑穀類を節約しながら食べていた民族とは違い、元々のネイティブアメリカンが狩りをしながら暮らしているところに、世界各国からの移民がいろいろな食文化を持ち込んでいるでしょうから、バラエティに富んだ豪快な食事に違いないと想像していました。
また、日本では今頃になって、トランス脂肪酸(マーガリンやショートニングなどのようにもともと液状の不飽和脂肪酸を水素添加して固形の飽和脂肪酸の形に加工する際にできる脂肪酸の事)は、体に良くないのでなるべく食べないほうが良いと言っています。しかし、私の記憶ではアメリカでは30年近く前にトランス脂肪酸は体に良くないので、摂取量を減らすように政府が指導していると聞いた。その時、なぜ日本は規制しないのかと調べたが、アメリカは5g/日位摂取し、日本では0.7g/日位だからほとんど問題ないと聞いた。だから、規制の必要がない…と。
アメリカは政府が国民の健康をリードしている。「保健先進国だ」「すすんだ国なんだ」と感じました。
その頃の私は、それ以上深くそのことを掘り下げて考えるすべもなく、何となく「そうなんだ」と中途半端に納得し、我が家ではマーガリンを食べるのをやめました。
アメリカの食をリードしているのは誰?
日本が牛肉の輸入自由化やスーパーができて食品の購買量が増え、大阪万博で盛り上がっていた頃、1968年、アメリカでは低所得者層の飢えが社会問題となり、『栄養と所要量に関する上院特別委員会―マクガバン委員会』が設立された。
マクガバン委員会は病気と食生活に関する調査を開始し、「食品、栄養と健康についてのホワイトハウス会議」を開いた。
1970年代、アメリカ心臓協会は脂質を全カロリーの35%以下、飽和脂肪酸を10%以下に、コレステロールを300mg以下にすることを推奨した。1977年2月、マクガバン委員会はこの年までに何度も公聴会を開き、『米国の食事目標』として報告した。この中には米国の栄養協会会長も加わっている。10大死因のうち6つの病気が食生活に大きく関連することがわかり、栄養の問題は栄養不足だけではなくなった。そして、病気にならないための食生活の目標が6つ設定されました。
- 炭水化物の比率を(全カロリーの)55~60%に増やす。
第2版で改定された⇒砂糖を足して炭水化物全体で58%とした。 - 現在40%の脂質を30%に減らす。
- 飽和脂肪酸を10%に減らす。多価不飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸を10%にする。
⇒これは飽和脂肪酸の摂取を減らすように肉類を選ぶに変更された。 - コレステロールを1日300mgに減らす。
⇒閉経前の女性、幼児、高齢者は卵の栄養を考慮してコレステロールの摂取量を減らすとされた。 - 砂糖を15%に減らす。
⇒これはその後10%以下に変更された。 - 塩分を3gに減らす。
⇒塩分は5gに変更された。
これらを実行するためには、全粒穀物、果物、野菜、鶏肉、魚、低脂肪乳を増やし、肉類、バター、卵、脂肪、砂糖、塩分を減らすことと報告されましたが畜産業界と砂糖業界の抗議や、研究が十分ではないという専門家が意見を送るなどがありました。
この後、「死に至る病に関する食事」の公聴会は、生産業界の見解を聞く公聴会を含め、全8回の公聴会が開催され、疾患との関係を示した多くの業界、研究者、政府担当官の意見が寄せられ資料として残され1977年12月「米国の食事目標-第2版」改訂版が出され、目標に、「肥満にならないように消費カロリー分しかエネルギーを摂取しないようにする」の文言が追加されました。
その後、何度も心臓協会や国立癌研究所が意見を発表したが、農務省の要職に畜産業界のロビイストが就任し、「食生活指針」に関する研究が閉鎖されることもあった。また、2005年、砂糖業界のロビー活動によって、「糖分のとりすぎを避ける」という記述が撤回されそうになったりしている。
食は自分自身の命をつなぐためのものだと思う
日本では1970年頃、万博が開催されて自動車所有率が増え家庭電化が進み、比例するように糖尿病が増え始めた。私は食に関してはなかなか疫学研究が反映しにくく、日本は生産業界やマスメディアの影響が強すぎて、消費者が偏った食生活に走っている例を聞くにつけ、「何とかできないか」と感じていた。しかし、アメリカも同じだったと知り、自分の健康は、自分で考えて守らなければいけないことを改めて考えるべきだと思った。よく、糖尿病治療で「治療の主治医はあなたですよ」という言い方をします。いくら良い薬を処方されても、服薬がいい加減だったり生活習慣の改善ができなければ血糖コントロールは改善されません。
江戸時代に、貝原益軒が83歳で書き終えた『養生訓』には、『食は飢えを防ぐためのものであって、好みのままに食べてはいけない。薄味であっさりしたものを腹八分にしましょう』とあります。
生活が洋風化したり、体格が良くなったからといっても、内臓までアメリカナイズされるわけではない。そろそろ原点に戻って、自分の体のために食事をしませんか?
アメリカ人は自分の意志で食事をしている?
実際にアメリカに行って感じたことは、菓子類が日本ほど安くないことと、地域にもよるのでしょうが、広くてそうそう簡単に買い物に行けないこと(ガソリンスタンドなどにコンビニのような店が併設されていて、ジュースや菓子類を買うことはできるが、弁当を買うついでにスィーツを買うという感じではない)、調理されたものや、半調理品の種類の多さにも驚きました。山のようにゴロゴロ積まれた野菜や果物の多さにアメリカは農業大国だということを改めて感じました。
ただ、アメリカでは知識があれば、ベジタリアンであろうが、ビーガンであろうが自分で選んで半調理品や調理済みの食品を購入できるということに感心しました。日本でも消費者が賢くなって、自分で考えて自分にとって適切な食事ができるようにならなければいけないと思いました。


次回はアメリカの食事(後編)
日本の食糧政策が気になって、アメリカと比較したくて調べていたら実際の食事が書けなくなってしまった。次回はアメリカを含め、今回行ったメキシコ、数年前に行ったフィジーの具体的な食事について書いてみたいと思います。
コラムニスト

管理栄養士 伊藤 教子
長年、管理栄養士として病院の給食管理・栄養管理に従事後、現在、内科糖尿病専門医院にて糖尿病を中心とする生活習慣病、高齢者の低栄養等の栄養食事指導をしています。
ライフワークとして「あなたの体は、あなたの食べたものでできている」ということを意識した「食」の啓発活動を行なっています。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
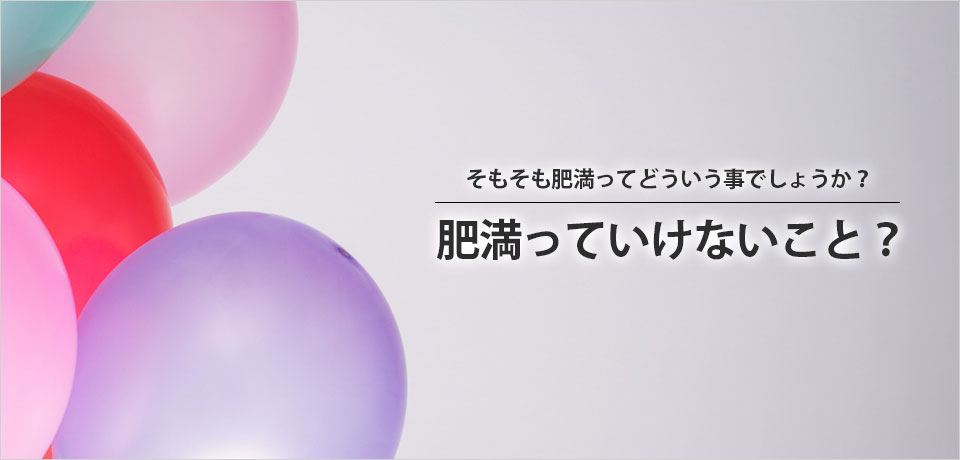 2020/06/17
2020/06/17前回、見た目を気にするフランス人がコロナ禍で、「平均2.5kg太ったらしい」という記事について書きました。
そこで同じように動かなくなって体重が気になるという方も多いのではないかと思い、今回も肥満について書いてみたいと思います。 そもそも肥満ってどういう事でしょ...続きを読む
-
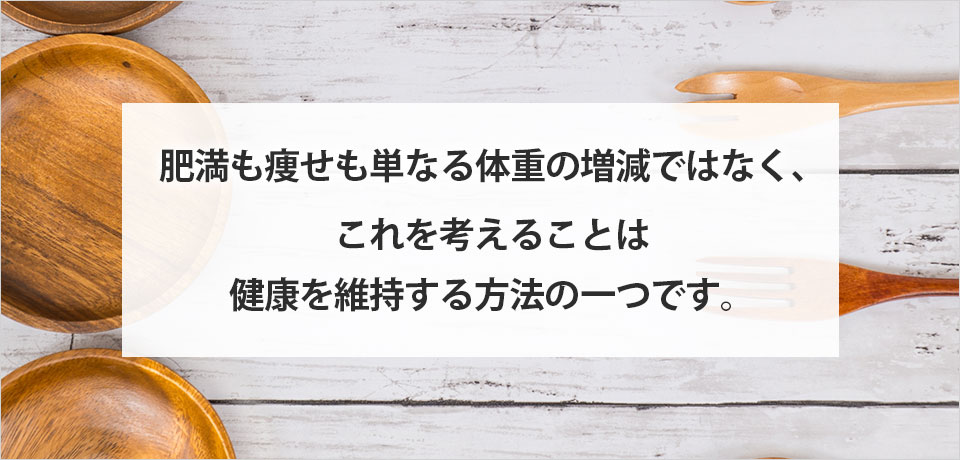 2020/07/15
2020/07/15今回は具体的に個々人の食べる量の適正量をお知らせする前に、どうしても知っておいていただきたいと思っている食事の摂り方の基本を書いてみました。
世界中でコロナウィルスの感染が広がり、思いもかけないことが起こっている。健康を維持する事だけではなくこの感染が広がることによって、それこそ死活問題で日々明日はど...続きを読む
-
 2021/03/19
2021/03/19自分がどれくらいの食塩を食べているのか、知ることから始めましょう。
上手に減塩をする際、日頃よく食べているものの塩分量を知ることが一番です。そこから先ずは外せそうなものを除くことから始めてみましょう。 つい先日、待合室の患者様...続きを読む
-
 2019/02/28
2019/02/28私はクリニックで、栄養指導をするとき際に「食事は3食召し上がっておられますか?」と必ずお聞きします。食事を3食食べているということは、生活全般を規則正しく過ごし...続きを読む




