
インプラントの歴史は、1952年、スウェーデンのブローネマルクが「オッセインテグレーション(骨とチタンの結合)」を発見したことに端を発します。
もともと応用生体工学研究所の所長だったブローネマルク博士はある大学の医学部で骨が治癒する過程において、骨髄がどのような役割を果たすかを研究していました。実験を終えて、ウサギのすねに埋め込んだ生体顕微鏡用のチタン製器具を取り出そうとしたところ、しっかりと骨にくっついてしまい、どうしてもはがすことができませんでした。それまでは他の金属類でそのような経験をしたことがなかったブローネマルク博士は大いにその現象に興味をもちます。その後、血液循環の研究などにおいても、彼は次々とチタンの特質を目の当たりにすることになります。それらの偶然の発見から、「チタンは骨に拒否反応をおこさず、結合する」ことを確信したのです。
これを彼はオッセオインテグレーション(骨結合)と命名し、以来さまざまな実験のすえ、歯科治療への応用を探り、1965年ついに人間に臨床応用したのです。
史上初のインプラント治療
ちなみに世界で始めてブローネマルク・システムによるインプラントの治療を受けたのは、ヨスタ・ラーソンという男性です。生まれつき顎の骨が弱く、数本しか歯が無かったそうですが、手術は無事に成功。
インプラントは彼が亡くなるまで40年間もの間、問題なく機能したそうです。
現在に至っても、インプラント治療は進化を続けています。
インプラントの進化
表面性状
- 機械研磨
ブローネマルクが発見した純チタンと骨との結合 - HA
チタン表面に骨と同じ成分であるHA(ハイドロキシアパタイト)を吹き付け、骨との結合能力を向上 - 酸処理、チタン顆粒吹き付け
チタン表面を酸処理したり、チタン顆粒をサンドブラスト処理する事で粗造にし、骨との結合能力を向上
形状
- ブレードタイプ
 現在では用いられないタイプです。板状で幅が狭く細いので比較的骨幅の狭い部分に用いることが可能です。現在主流のスクリュータイプに比べインプラント本体の一部に力が集中しやすく、破損や骨吸収が起きやすいという欠点があります。
現在では用いられないタイプです。板状で幅が狭く細いので比較的骨幅の狭い部分に用いることが可能です。現在主流のスクリュータイプに比べインプラント本体の一部に力が集中しやすく、破損や骨吸収が起きやすいという欠点があります。 - スクリュータイプ
 インプラントの直径が先端にいくほど細くなり、ネジのようなかたちをしています。ブレードタイプに比べ埋め込む穴が小さくてすみ、噛む力も効率よく骨に伝えることができます。現在のインプラントの形状の主流です。
インプラントの直径が先端にいくほど細くなり、ネジのようなかたちをしています。ブレードタイプに比べ埋め込む穴が小さくてすみ、噛む力も効率よく骨に伝えることができます。現在のインプラントの形状の主流です。 - シリンダータイプ
 円筒形で上部と下部が同じかたちをしており、ネジが切ってないタイプ。スクリュータイプ以前は主流でした。
円筒形で上部と下部が同じかたちをしており、ネジが切ってないタイプ。スクリュータイプ以前は主流でした。 - 中空タイプ
 外見はスクリュータイプに似ていますが、中は中空で側面にも複数の穴があります。中が中空のためインプラントの周囲や中までも骨が取り囲むので、骨との接触面積が広く、噛む力を効率的に伝えることができます。が、強度的に弱く破損のリスクが高い。
外見はスクリュータイプに似ていますが、中は中空で側面にも複数の穴があります。中が中空のためインプラントの周囲や中までも骨が取り囲むので、骨との接触面積が広く、噛む力を効率的に伝えることができます。が、強度的に弱く破損のリスクが高い。
ナローインプラント
ナローインプラントは狭い骨幅に対応できるような細いタイプのインプラントで、チタンに非常に強度の高いジルコニアを合成する事でインプラントの強度を上げ、細いインプラントを可能にしたものです。ナローインプラントに関する詳細は、下記の記事を参考になさってください。
ショートインプラント
ショートインプラントは骨の高さが足りない場合に対応できる非常に短いタイプのインプラントで、骨とインプラントの結合力の進歩により実現可能になったものです。ナローインプラントについて詳しくお知りになりたい方は、下記の記事を参考になさってください。
インプラント治療のこれから
インプラントは世界中に100種類以上存在していて、そのうちの30種類程度が日本でも流通しています。
各種メーカーがインプラントの開発を進めてきましが、形状はスクリュータイプ、表面性状も多様な方法で表面を粗造にする事で進化は固まってきたように思われます。 近年の主要な変化はナローインプラント、ショートインプラントの確立であるだろう。これにより、狭い骨、高さのない骨などあらゆるタイプの骨にインプラントを適用できるようになってきました。
次回のコラムではナローインプラント、ショートインプラントについて深く掘り下げて行きます。
- カテゴリー:歯科
- インプラント オッセオインテグレーション チタン 歯科治療
コラムニスト|医療法人KDCかみなか歯科 理事長:上中 茂晴
所在地・アクセス
〒738-0025 廿日市市平良1-17-50 Tel:0829-20-4888- JR廿日市駅から徒歩7分・広電廿日市駅から徒歩7分
- JR廿日市駅から車で2分のところのセブンイレブン前にかみなか歯科はございます。

理事長 上中 茂晴
広島県にある廿日市市平良「精密な検査とカウンセリング。原因から改善して、治療する」をモットーに、大阪で10年間勤務し、学んだ最先端の技術を、郊外でも最新の治療を提供すべく地域密着型の治療を提供している「かみなか歯科」です。
● 拡大鏡、歯科用顕微鏡を用いて7倍から20倍に拡大した視野のなか行う精密治療
● CTも用いた3次元診断
● 歯科麻酔医による全身管理の元、安全に行う外科処置
の3つの特徴を軸に安心、安全な治療を提供しております。
800本以上のインプラントを埋入してきた確かな実績を元に、CT分析ソフトを用いた事前シミュレーションと、歯科麻酔医による全身管理のもと安全に手術に臨めています。痛みや腫れが少ない麻酔を使用して、寝ている間に手術を終えることが可能です。
また、歯の温存を図る歯周病治療として、歯のクリーニングを行う機器の中で最も歯茎への負担が少ない「エアーフローマスター」を導入。歯周病菌の状況や変化も動画撮影し、口内のリスク管理を行います。歯周病により失った骨を再生させる再生療法を行う資格も取得しております。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
 2021/10/06
2021/10/06患者様から良く「インプラントは虫歯にならないから一生保つよね?」と聞かれます。
患者様から良く「インプラントは虫歯にならないから一生保つよね?」と聞かれます。 確かに、インプラントは人工物なので虫歯で穴が空く、なんて事はありえません。 ...続きを読む
-
 2019/02/28
2019/02/28現在のチタン製歯科インプラントによる治療が始まって約50年 その歴史の中で診断技術を飛躍的に伸ばしたのがCTによる顎骨診査でありさらにそのデジタルデータは...続きを読む
-
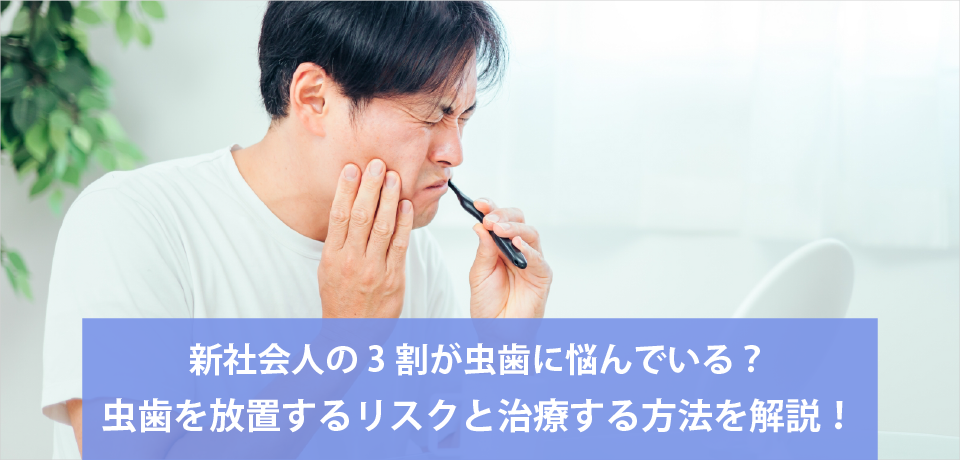 2024/08/22
2024/08/22株式会社Zenyum Japanが行った「新社会人の歯に関する意識調査」では、第4位に虫歯がランクインしました。虫歯が全体の29.2%を占めており、かなりの数の...続きを読む
-
 2020/03/30
2020/03/30ショートインプラントとは、長さが8mm以下の短いインプラントの事を言います。
ショートインプラントとは、長さが8mm以下の短いインプラントの事を言います。 現在超高齢社会を迎えた日本において、インプラント患者の高齢化により全身状...続きを読む





