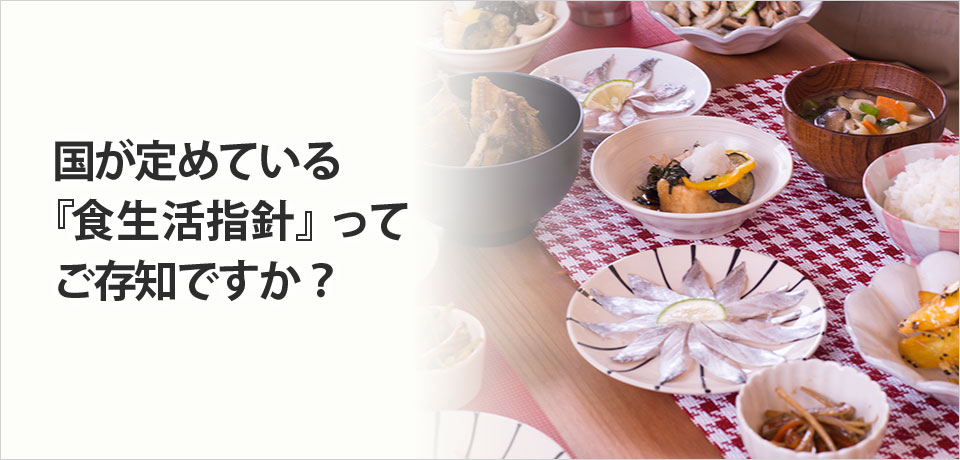
前回、「和食」が無形文化財に登録されたが、それは少し前の日本食であって、今はそれとはかなり違った食生活になっているということを書きました。
そこで、今回は、国は食事についてどのようなことを問題だと考え、どのような方向性を示しているのかという『食生活指針』について書いてみたいと思います。 私は管理栄養士という職業柄、なぜ政府が先頭に立って、もっと啓発活動を推し進めないのかと思っています。『食生活指針』について、知っていただきたいので書くことにしました。
「食生活指針」ってなに?

戦争当時の食生活指針には、食糧難を切り抜けることを目的とし、主食には玄米が推奨され、雑穀や野草など食料になるものについて書かれ、戦後、厚生省はアメリカの援助を得て栄養改善運動をすすめ、生活が豊かになるにつれ、おかずの多い欧米風の食生活を普及させたが、その結果として生活習慣病が増加し、1983年(昭和58年)に農林水産省が日本型食生活を提唱し、1985年(昭和60年)厚生省が、「健康づくりのための食生活指針」を策定しました。
指針の中身
- 主食、主菜、副菜をそろえて
- 一日30食品を目標に
- 動物性の脂肪より植物性の油を多めに
- 食塩は一日10グラム以下を目標に
- こころのふれあう楽しい食生活を

というようなもので、生活の質に言及していることが特徴的だと言われています。ただ、私も覚えているが、「一日30品目って、どうやって食べさせようか」と食材を数えたものです。
平成12年に、『最近の我が国における食生活は、健康・栄養についての適正な情報の不足、食習慣の乱れ、食料の海外依存、食べ残しや食品の廃棄の増加等により、栄養バランスの偏り、生活習慣病の増加、食料自給率の低下、食料資源の浪費等の問題が生じている。 このような事態に対処して、国民の健康の増進、生活の質の向上及び食料の安定供給の確保を図るため』ということで、初めて当時の文部省、厚生省、農林水産省の3省が連携して策定されました。
平成12年の食生活指針が策定されてから16年が経過し、平成28年に改定がされました。この間、平成17年に食育基本法が制定され、10年計画の国民の健康づくり運動が平成25年にスタート。この年の12月に和食が日本人の伝統的な食文化として、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。そして平成28年4月に5年計画の『第3次食育推進基本計画』がスタートし、これを踏まえて食生活指針が改定されました。
この食生活指針は国民に実践してほしい内容が10項目にまとめられています。
国が国民に示す「実践してほしい10項目」とは

現在の食生活指針の大きな特徴は、食料の生産・流通から食卓、健康まで、食生活全体を視野に入れて作成されていることです。QOLの向上を重視し、バランスのとれた食事内容を中心に、食料の安定供給や食文化、環境にまで及ぶ内容で、10項目の指針とその具体的な取り組み内容が示されています。
(1).食事を楽しみましょう。
- 毎日の食事で、健康寿命をのばしましょう。
- おいしい食事を、味わいながらゆっくりよく噛んで食べましょう。
- 家族の団らんや人との交流を大切に、また、食事作りに参加しましょう。
(2).1日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを。
- 朝食で、いきいきとした1日を始めましょう。
- 夜食や間食はとりすぎないようにしましょう。
- 飲酒はほどほどにしましょう。
(3).適度な運動とバランスのよい食事で、適正体重の維持を。
- 普段から体重を量り、食事量に気を付けましょう。
- 普段から意識して身体を動かすようにしましょう。
- 無理な減量はやめましょう。
- 特に若年女性のやせ、高齢者の低栄養にも気を付けましょう。
(4).主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
- 多様な食品を組み合わせましょう。
- 調理方法が偏らないようにしましょう。
- 手作りと外食や加工食品・調理食品を上手に組み合わせましょう。
(5).ごはんなどの穀類をしっかりと。
- 穀類を毎食とって、糖質からのエネルギー摂取を適正に保ちましょう。
- 日本の気候・風土に適している米などの穀類を利用しましょう。
(6).野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせて。
- たっぷり野菜と毎日の果物で、ビタミン、ミネラル、食物繊維をとりましょう。
- 牛乳・乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などで、カルシウムを十分にとりましょう。
(7).食塩は控えめに、脂肪は質と量を考えて。
- 食塩の多い食品や料理を控えめにしましょう。
食塩摂取量の目標値は、男性で1日8g未満、女性で7g未満とされています。 - 動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよくとりましょう。
- 栄養成分表示を見て、食品や外食を選ぶ習慣を身につけましょう。
(8).日本の食文化や地域の産物を活かし、郷土の味の継承を。
- 「和食」をはじめとした日本の食文化を大切にして、日々の食生活に活かしましょう。
- 地域の産物や旬の素材を使うとともに、行事食を取り入れながら、自然の恵みや四季の変化を楽しみましょう。
- 食材に関する知識や調理技術を身につけましょう。
- 地域や家庭で受け継がれてきた料理や作法を伝えていきましょう。
(9).食糧資源を大切に、無駄や廃棄の少ない食生活を。
- まだ食べられるのに廃棄されている食品ロスを減らしましょう。
- 調理や保存を上手にして、食べ残しのない適量を心がけましょう。
- 賞味期限や消費期限を考えて利用しましょう。
(10).「食」に関する理解を深め、食生活を見直してみましょう。
- 子供のころから、食生活を大切にしましょう。
- 家庭や学校、地域で、食品の安全性を含めた『食』に関する知識や理解を深め、望ましい習慣を身につけましょう。
- 家族や仲間と、食生活を考えたり、話し合ったりしてみましょう。
- 自分たちの健康目標をつくり、よりよい食生活を目指しましょう。
『食生活指針』を実行するためにはどうすれば良いのでしょう
これら10項目の目標は、まず(1)で健全な食生活をどう楽しむかを考え、(2)〜(9)の内容を実践しながら、(10)で食生活をふり返り、改善していこうという、我々のような食に携わるものとしてはこれ以上の内容はないと思うくらい、細部にまでこだわった内容となっています。
しかし、現在の日本には食情報があふれ、いくら正しい食生活をしたいと思っても日々いろいろな情報が発信されて「いったい何を信じてよいのやら」と、皆さんが右往左往するのも無理はないと思うほどです。 ただ言えることは、そんなに楽をして、したい放題のことをして健康が手に入るとは思えないということです。そして、この10項目を実行するのは今の我々の生活ではかなり難しいということです。
次回はこの食生活指針と照らし合わせながら、まず、子育て中の若いお母さんたちに私の考える範囲のことですがお願いしたいことを書いてみたいと思います。
コラムニスト

管理栄養士 伊藤 教子
長年、管理栄養士として病院の給食管理・栄養管理に従事後、現在、内科糖尿病専門医院にて糖尿病を中心とする生活習慣病、高齢者の低栄養等の栄養食事指導をしています。
ライフワークとして「あなたの体は、あなたの食べたものでできている」ということを意識した「食」の啓発活動を行なっています。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
 2022/01/26
2022/01/26健康のために『バランスの良い食事をしましょう』っていうけど「バランス」の良い食事ってどんな食事でしょうか?
私は、日々クリニックで糖尿病、高血圧、脂質異常症等の患者様に食生活の状況をお聞きし、「△△のような食品が食べ過ぎですね」とか「○○のような食品が足りませんね」な...続きを読む
-
 2020/01/15
2020/01/15食生活指針に謳われていることは、実際にはどれくらい実行されているのでしょうか
食生活に関する環境が驚く速さで変わってきています。私が自分の家族を例に考えてみてもかなり変わってきています。仕事で夜遅い帰宅の父親と、せめて1日一度は顔を合わせ...続きを読む
-
 2020/05/15
2020/05/15今回は新生活を迎える方たちへ、食生活のアドバイスをするつもりでしたが、
予定を変更してコロナ禍の中での食生活について書きたいと思います。 新型コロナウィルスの所為で世界中が大変なことになってしまいました。こんなに発達した現代で...続きを読む
-
 2019/09/02
2019/09/02待望のアメリカ旅行に行ってきました。私の中で憧れのアメリカというのは、サンフランシスコやニューヨークといった華やかな感じのイメージではなく、なぜだか開拓時代のアメリカなのです。
私が初めて憧れたアメリカは1970年代に書かれた『大草原の小さな家』の舞台であるミネソタの草原、ブッシュに実るベリー類、それらで作るお菓子やスープ。丸太小屋に飾...続きを読む




