
小学生のお子さんが「スマホを持ちたい」と言った時、親としては持たせるか、まだ早いか、判断に迷うこともあるかもしれません。
今回は子どもの初めてのスマホ使用について、今の社会の状況・何か弊害はないのか・子どもにはどう説明するか…などを解説します。
スマホを持っている小学生の割合は?
2020年4月に東京都が発表した調査結果によると、小学生700人のうちスマホを持っている割合は、低学年19.0%、高学年34.6%となりました。
わが子は「みんなスマホ持ってるよ!」と言うけれど、意外とそうでもないな…と感じたのではないでしょうか。
2018年の別の調査では、緊急時の連絡のため携帯電話を持たせる場合でも、従来のいわゆる「ガラケー」を使用している家庭も多く、低学年ではスマホとガラケーの比率は1:6、高学年でも2:3程度のようです。
とはいえ、最新のデータと比べれば、年々スマホの率が上がっていることは確かでしょう。
小学生にスマホ、弊害はない?
小学生にスマホを持たせることについて、親の立場からみた心配ごとには次のようなものがあります。
- 視力の低下
- 睡眠不足
- 依存的になる
- 学習時間が削られる
上記はいずれも、適切な使用時間ならあまり問題はないですが、使いすぎてしまうと弊害となります。
また、
- インターネットを通じ犯罪に巻き込まれる
- 個人情報を書き込んでしまう
- 有害サイトにアクセスしてしまう
- ゲームなどで高額の課金をしてしまう
- SNSの中で悪口やいじめの被害者または加害者になる
といったトラブルの心配もあります。
「まだ早い」子どもにどう説明する?
上記の懸念を考え、やはりもう少し大きくなってから…と判断した場合、お子さんにはどう説明するのがよいでしょうか。
経験者のママ・パパに、どう伝えたか聞かせてもらったところ、やはり「スマホで何をしたいのか」を確認して判断したという人が多いようです。
「4年生の息子に、なぜ従来の携帯ではなくスマホがいいのか聞いてみると、動画が見たいとのことでした。まったく動画を見させたくない訳ではないですが、無制限に見るのはよくないと思い、高学年になるまでは、父親のタブレットを時間を決めて貸すのでそれで見るように話しました」
「3年生の娘に理由を聞くと、好きな芸能人や流行りのSNSを見たいとのことでした。しかしいくつかのSNSには年齢制限があるので、中学生でないと見られないからそれまで待とうねと話しました」

ちなみに、芸能人も投稿しているInstagramやTwitter、若者に人気のTikTokなどのスマホアプリは、ダウンロードやユーザー登録はいずれも13歳以上からと規約で決められています。(2021年3月現在)
また、スマホ使用にともなうリスクを実例でいくつか説明し、
「インターネットの世界ではどんどん新しい犯罪が出てくるけど、パパやママは、たくさんの危険に小学生のあなたが1人で対処するのはまだ難しいと思う」
と、もう少し成長してから…という方針を伝えた人もいました。
スマホを持たせるときの約束事や注意点
一方、「スマホを持たせてもよい」と判断した人は、お子さんとどのような約束やルールを決めていたのか、いくつか紹介します。
- 使用時間を決め、それ以外はリビングで充電するなど手もとに置かない
- 帰宅後は宿題が終わるまで使わない
- 個人情報や悪口をネット上に書かない
- 自分の身体の写真などをスマホで誰かに送らない
- 壊れたり落としたりしたら、お年玉やお手伝いで費用を出す
- 歩きスマホはしない
- アプリをダウンロードするときは相談する
- ゲームやアプリで課金が発生するときは相談する
- 有害サイトやSNSには親がフィルタリングをかける
アメリカで、ある母親がわが子のために作った「スマホ18の約束」は、多くの中学校や、最近は小学校でもよく取り上げられますので、参考にしてみるのもいいですね。
重要なのは、上記を親が一方的に決めて押しつけるのではなく、子どもも一緒に考えて納得した上でスタートすること。
小学校高学年では、まず子どもに思いついたものを書いてもらい、それをたたき台にして親子で話し合ったという人もいました。
低学年の場合は「よる○時を過ぎたら使わない」などの穴埋め式にして、子どもに考えさせてみるのもいいですね。
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
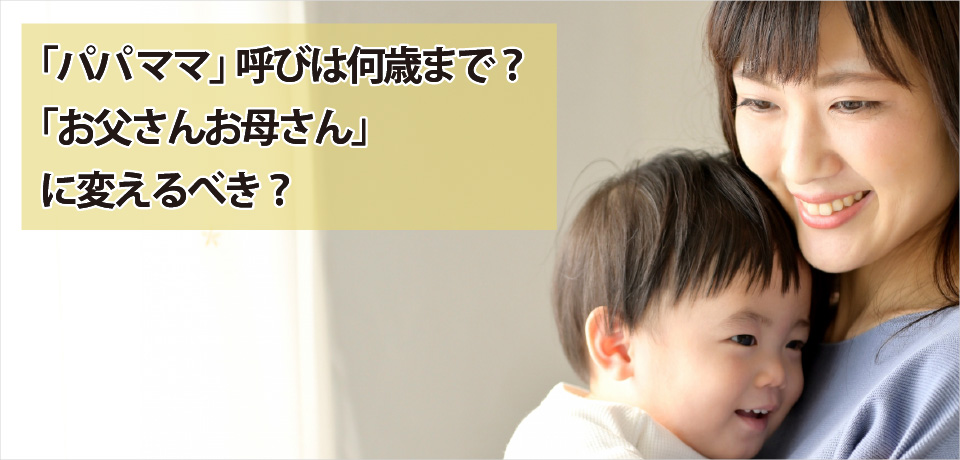 2021/07/02
2021/07/02赤ちゃんが生まれると、毎日のように「ママですよ~」「パパとお風呂に入ろうね」などと呼びかける機会があり、そのうち赤ちゃんも「ママ」「パパ」と呼ぶようになります。
とても幸せな育児の1コマですが、お子さんが成長してくると、ふと「いつまでもパパ・ママと呼ばせていいのかな?」と迷うことがあるかもしれません。 そこで今回は...続きを読む
-
 2021/04/30
2021/04/30小学生のお子さんが「スマホを持ちたい」と言った時、親としては持たせるか、まだ早いか、判断に迷うこともあるかもしれません。
今回は子どもの初めてのスマホ使用について、今の社会の状況・何か弊害はないのか・子どもにはどう説明するか…などを解説します。 スマホを持っている小学生の割合は?...続きを読む
-
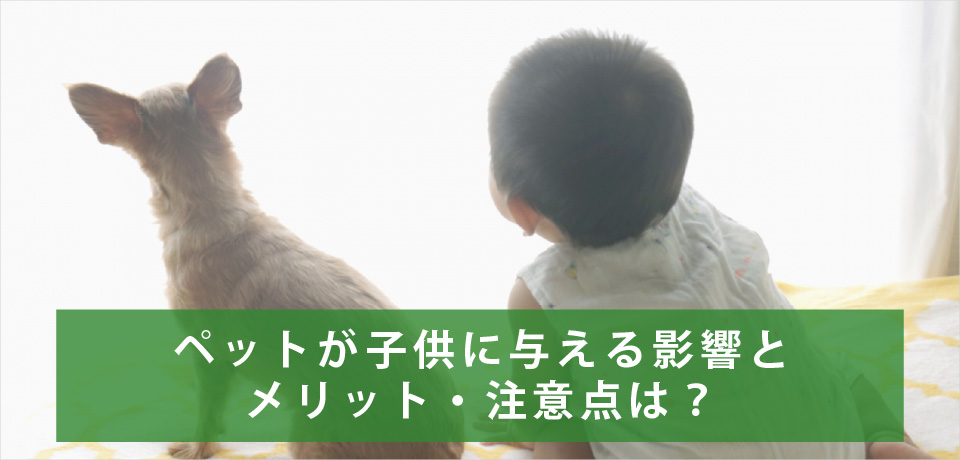 2023/04/19
2023/04/19皆さんの中に、ペットと暮らしながら子育てしているお宅はどのくらいいらっしゃるでしょうか。
ペットはいないという家庭でも、お子さんが3~4歳から小学校低学年くらいになると、お友達の家や絵本・アニメなどの影響で「ワンちゃんを飼いたい」と言い出したり、ショ...続きを読む
-
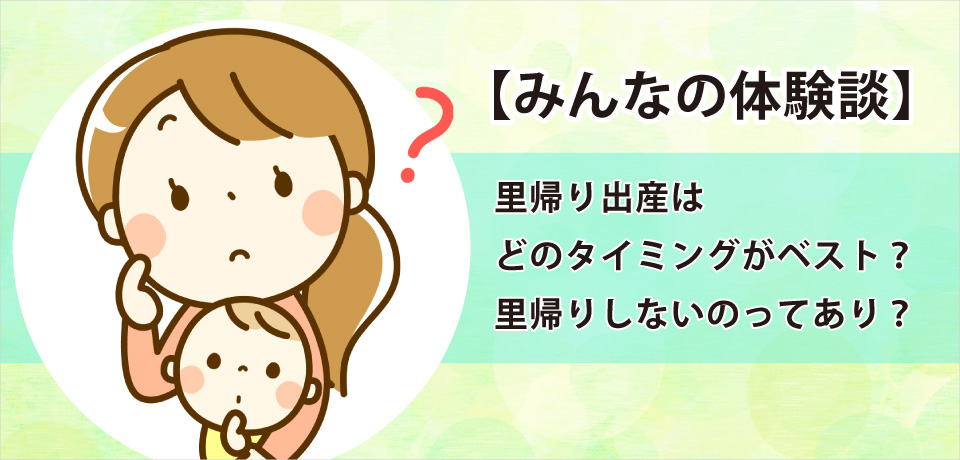 2021/04/12
2021/04/12「夫の仕事がハードで出産前後を夫婦だけで乗り切るのが難しい」「上の子を見てくれる人がいない」などで、ママの身体が回復するまで実家に滞在する「里帰り出産」。
2020年はコロナ禍で感染拡大地域からの里帰り出産をできるだけ控えるように要請もありましたが、さまざまな事情でやむを得ず里帰り出産を選択する人もいるかと思います...続きを読む




