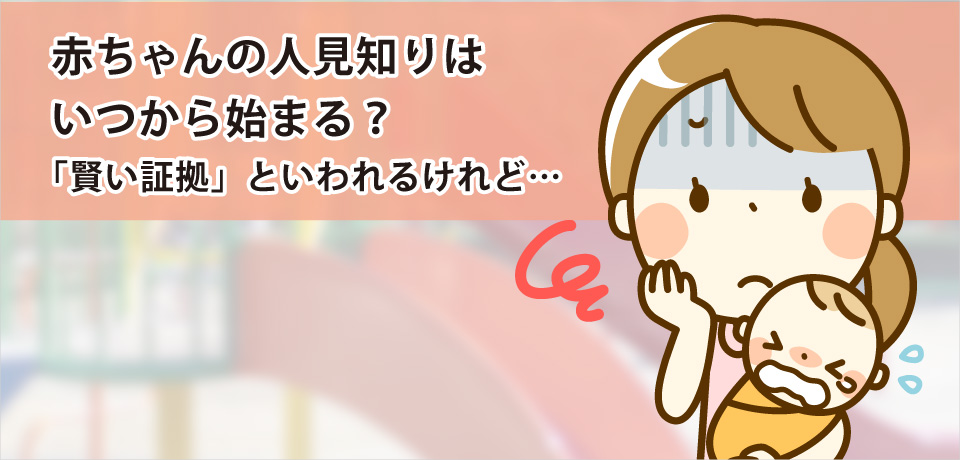
赤ちゃんが、家族以外の人に話しかけられるとママにしがみついて顔を隠してしまったり、だっこしようとすると泣いて嫌がったりする「人見知り」。
ママからすると、あまり赤ちゃんの人見知りが強いと、相手に対して気まずい思いもするし、人に預けにくくて困ってしまいますよね。
その一方で、あまり人見知りをしない赤ちゃんを「うちの子、大丈夫かな」と心配している人もいるかもしれません。
今回は、一般的な人見知りが始まる時期や、人見知りする赤ちゃんの心理、「人見知りするのは知恵がついてきた証拠」とよく聞くけれど本当なのか…などの疑問についてお話しします。
人見知りが始まるのはいつごろ?

一般的には、赤ちゃんが人の顔を見て身近な人とそうでない人を区別し近付こうとしない「人見知り」は、生後6ヶ月から8ヶ月頃に始まるとされています。
生後まもない赤ちゃんは「お世話してくれる誰か」がいればよく、誰がだっこしてくれてもあまり嫌がることはありません。
3ヶ月頃からだんだんと特定の相手(おもにママ)の側にいたがるようになり、6ヶ月を過ぎると、それまでは他の人がだっこしても泣かなかったのが、泣いて嫌がる子が増えてきます。
ただ上記の時期や度合いはかなり個人差があり、生まれつきの気質や、大家族かそうでないか、保育園に通っているかどうか…などでも人見知りの表れ方は違ってきます。
参考
人見知りするときの赤ちゃんの気持ち
生まれたばかりの赤ちゃんには「快・不快」の感覚しかなく、成長するにつれて喜怒哀楽といった感情がどんどん増えてきます。
そして「恐怖」の感情は生後6ヶ月頃から発達してくるため、よく知らない人に対して「怖い」と感じ、人見知りをすると考えられてきました。
しかし最近の研究では、どうやら人見知りする赤ちゃんには「怖い」のみではなく、同時に「近付きたい」という、2種類の心理の葛藤があると分かってきたそうです。
人見知りの強い赤ちゃんは、誰かが話しかけたりだっこしようとしたりすると泣くけれども、少し離れると、ママにしがみつきながらもじっと相手を観察している様子が見られるということです。
2人・3人とお子さんを育てた経験のある人なら「ああ、そうそう」とうなずけるのではないでしょうか。
参考
人見知りする子は「賢い子」?
ところで、子育ての先輩から「人見知りするのは賢い証拠よ」といった話を聞いたことはありませんか?
そして「うちの子ほとんど人見知りしないけど、発達に問題があるのかな」と不安になっている人もいるかもしれません。
たしかに、いつも一緒にいて愛着を示す相手と警戒する相手を区別できるのは成長したからこそですが、人見知りをしない子だって、ママと他の人の区別はしっかりとできているはず。
そもそも、赤ちゃんは新生児期から声や匂いで母親が分かっていて、生後4日でもママと他の人の声を区別できるという研究報告もあります。パパの声も生後2週間で聞き分けられるということです。
慣れない相手に対して、あまり警戒せずにコミュニケーションを取ろうとする赤ちゃんもいれば、慎重に観察してから近付こうとする赤ちゃんもいて、それはあくまでその子の性格であり、けして賢さの差ではないといえるでしょう。
「賢いから人見知りする」と言われるのは、赤ちゃんの後追いでトイレにもゆっくり入れなかったり、帰省時の集まりで親戚の顔を見るなり赤ちゃんが泣き出してしまい、きまりの悪い思いをしているママを、なぐさめたりフォローするために生み出された「育児の知恵」なのかもしれません。
参考
おわりに
0~1歳台の強い人見知りは2歳頃までにしだいに消失していきますが、赤ちゃん時代に人見知りが強いと、学童期以降も比較的多くの子でその傾向が続くといわれています。
また、まったく人見知りしない子のパパやママは、ある程度成長するまでは連れ去りなどが心配で人一倍目が離せないこととでしょう。
きょうだいでもそれぞれ違う「人見知り」、ママやパパは大変なときもありますが、これがこの子の個性なんだと思って、成長の過程を見守っていけるといいですね。
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
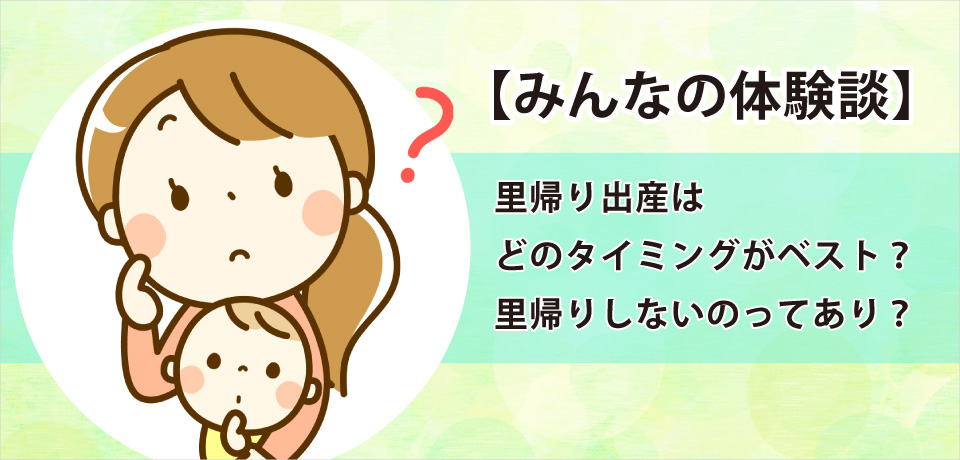 2021/04/12
2021/04/12「夫の仕事がハードで出産前後を夫婦だけで乗り切るのが難しい」「上の子を見てくれる人がいない」などで、ママの身体が回復するまで実家に滞在する「里帰り出産」。
2020年はコロナ禍で感染拡大地域からの里帰り出産をできるだけ控えるように要請もありましたが、さまざまな事情でやむを得ず里帰り出産を選択する人もいるかと思います...続きを読む
-
 2021/12/13
2021/12/13赤ちゃんが生まれて、今年はじめてのクリスマスを迎えるママ・パパは、家族でクリスマスパーティをしたいけど、
まだおすわりやハイハイの赤ちゃんでも楽しめるかな?と迷っている方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、離乳食でも雰囲気を味わえるクリスマスケーキや、...続きを読む
-
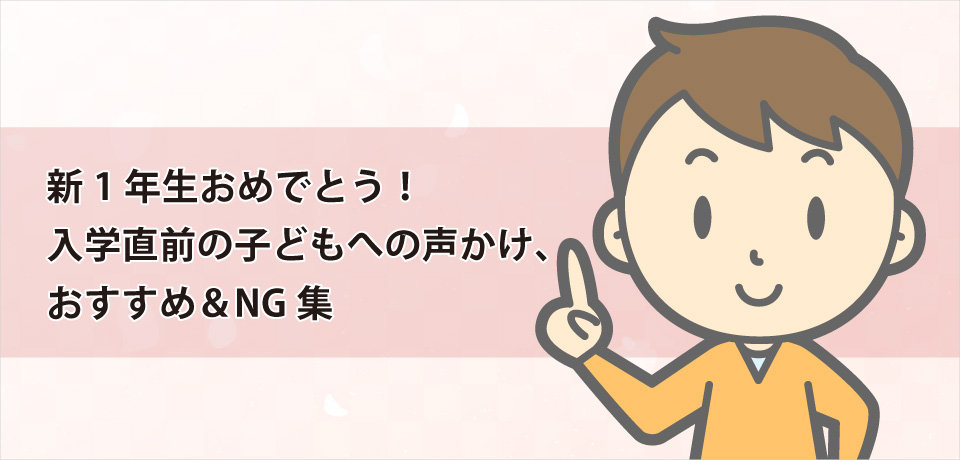 2021/03/25
2021/03/254月に新入学を控えたお子さんと親御さんは、いよいよ近付いてきた小学校生活に、期待と不安でいっぱいなのではないでしょうか。
ランドセルや文房具など、モノの準備は着々と進んできたことと思いますが、お子さん自身の心の準備はいかがでしょうか? 今回は、小学校に入学する直前の子どもに、...続きを読む
-
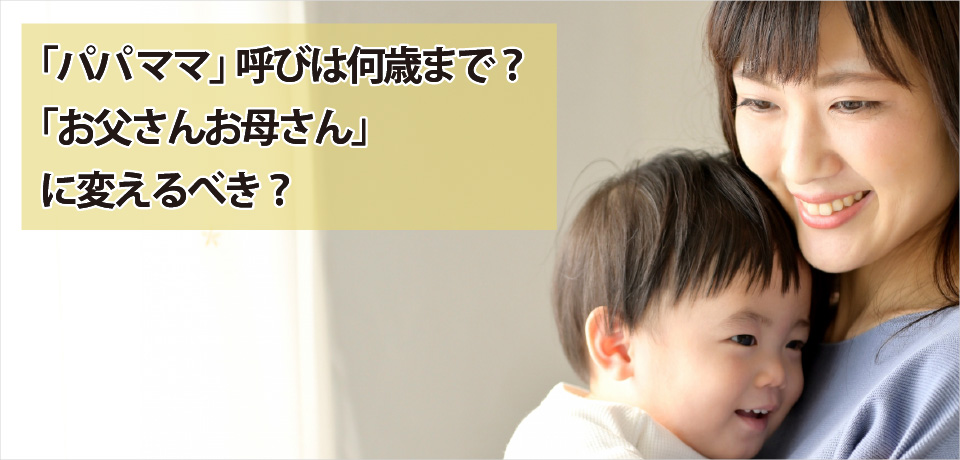 2021/07/02
2021/07/02赤ちゃんが生まれると、毎日のように「ママですよ~」「パパとお風呂に入ろうね」などと呼びかける機会があり、そのうち赤ちゃんも「ママ」「パパ」と呼ぶようになります。
とても幸せな育児の1コマですが、お子さんが成長してくると、ふと「いつまでもパパ・ママと呼ばせていいのかな?」と迷うことがあるかもしれません。 そこで今回は...続きを読む




