
よくなったり悪くなったりを何度もくり返すアトピー性皮膚炎。
寝ている間に無意識にかきむしって出血したり、かきすぎて皮膚がボロボロになったりとつらい思いをしている方が多くいるかと思います。
赤くなった皮膚を隠すために真夏でも長袖を着たり、人前に出るのが嫌になったりしてしまう方もいるでしょう。
今回は、アトピー性皮膚炎の治療に使える市販薬の選び方や実際の商品などについて詳しく解説します。
アトピー性皮膚炎は皮膚科を受診して治療することが基本となりますので、あくまでも病院の薬を切らしてしまったときのつなぎの薬を探す目的でご覧いただけると幸いです。
そもそもアトピー性皮膚炎とは?

日本皮膚科学会では、『増悪と軽快を繰り返す掻痒のある湿疹を主病変とする疾患であり、患者の多くは「アトピー素因」を持つ』状態をアトピー性皮膚炎として定義しています。アトピー素因とは、家族歴やアレルギー鼻炎、IgE抗体が作られやすい体質などのことです。
IgE抗体はアレルギー反応に関係している物質で、アトピー性皮膚炎のほかに蕁麻疹やアレルギー性結膜炎などにも関与しています。
参考
アトピー性皮膚炎になる原因
アトピーになる原因には、多くのものがあります。
- アトピー素因をもっている
- 皮膚のバリア機能が低下している
- 食物やダニ、ほこりなどのアレルゲンに接する機会が多い
- 汗や化粧品などで皮膚がダメージを受けやすい
- 寝不足が続いている
- ストレスがたまっている
一つではなく複数の原因が影響してアトピー性皮膚炎を発症することも少なくありません。
バリア機能の低下は、よく見られる原因の一つです。皮膚のバリア機能を守るのに必要なセラミドが低下している方が多く、皮膚が刺激を受けやすい状態になっています。
アトピー性皮膚炎で見られる症状
アトピー性皮膚炎は、左右対称に見られる湿疹が代表的な症状です。湿疹は膝や肘、首回りや顔などによく見られます。治ったと思ったらぶり返してしまうのも特徴です。多くは乳幼児や小児のうちに発症します。
年齢が上がるにつれてアトピー性皮膚炎の方は減っていく傾向にありますが、大人になってから初めて発症する方もゼロではありません。ここで注意したいのは、症状だけを見て自己判断でアトピー性皮膚炎だと決めつけないことです。
- 皮膚のかゆみが続いている
- 左右対称に湿疹ができている
- 症状をくり返している
このような場合は、まず皮膚科を受診して原因を明らかにしましょう。
アトピー性皮膚炎に使える市販薬の選び方
湿疹の状態によって選ぶべき市販薬は大きく変わります。なんとなく選んでしまうとまったく効かず症状が悪化することもあるので注意してください。
ステロイド剤の強さで選ぶ
ステロイド剤は、強さに応じて5つにランクわけされています。
| 強さ | 代表的な処方薬 | 代表的な市販薬 |
|---|---|---|
| ストロンゲスト | ・デルモベート(クロベタゾールプロピオン酸エステル) ・ダイアコート(ジフロラゾン酢酸エステル) | なし |
| ベリーストロング | ・フルメタ(モメタゾンフランカルボン酸エステル) ・アンテベート(ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル) ・マイザー(ジフルプレドナート) | なし |
| ストロング | ・ベトネベート、リンデロンV(ベタメタゾン吉草酸エステル) ・フルコート(フルオシノロンアセトニド) | ・ベトネベートN軟膏AS(ベタメタゾン吉草酸エステル) ・リンデロンVs(ベタメタゾン吉草酸エステル) ・フルコートf(フルオシノロンアセトニド) |
| ミディアム | ・リドメックス(プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル) ・ロコイド(ヒドロコルチゾン酪酸エステル) ・オイラゾン( デキサメタゾン) | ・コートf AT(プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル) ・セロナ(ヒドロコルチゾン酪酸エステル) |
| ウィーク | ・プレドニゾロン(プレドニゾロン) | ・クロマイ-P軟膏AS(プレドニゾロン) ・コートf MD軟膏(プレドニゾロン) |
市販薬ではストロングまでの成分しか扱いがありません。ベリーストロングやストロンゲストなどの処方薬の代替品は市販にはないので注意してください。
かきすぎによるカサブタや少数の丘疹ができている中等症の方、皮膚が乾燥しており軽い紅斑や皮膚のカサカサがある軽症の方は、市販の塗り薬でも対応できます。
ただし、基本は医師が皮膚の状態を見てステロイドの強さを決めるため、自分で選んで決めるというのはおすすめできません。
また、処方薬と同じ成分が含まれている市販の塗り薬でも含まれているステロイドの濃度が異なるものもあります。同じ成分だから同じ効果が期待できるとは限りません。
じゅくじゅくが気になる方は亜鉛華軟膏を選ぶ
アトピー性皮膚炎を治療していくためには、皮膚の保湿や保護を行っていくことも大切です。亜鉛華軟膏には皮膚を保護したり浸出液を吸収したりする働きがあります。患部のじゅくじゅくが気になる方はステロイド剤とあわせて使用すると症状がよくなりやすいでしょう。
塗り薬が効かないときは漢方薬も使われる
医師の指示通りに塗り薬を使用しても症状の改善が見られない場合は、漢方薬が使われることもあります。
ただし、漢方薬がアトピー性皮膚炎にどのくらい有効なのかを調べた試験はこれまであまり行われていません。そのため、漢方薬のみを使うのではなく、ステロイド剤と併用しながら治療をしていくのが望ましいと考えられます。
【塗り薬】アトピー性皮膚炎に使える市販薬
では、ここからはアトピー性皮膚炎に使える市販薬について見ていきましょう。
リンデロンVs軟膏
-

- リンデロンVs軟膏は、ストロングに分類されるベタメタゾン吉草酸エステルが配合された塗り薬です。軟膏のほかに、クリームやローションもあります。クリームは広範囲に伸ばしやすいというメリットがありますが、ジュクジュクしている部分には向きません。また、軟膏よりも刺激が強いため、アトピー性皮膚炎の方は軟膏タイプを選ぶのが無難でしょう。
フルコートf軟膏
-

- ストロングに分類されるフルオシノロンアセトニドが主成分の塗り薬です。抗生物質であるフラジオマイシン硫酸塩も配合されています。炎症を抑えながらかき壊しによる化膿を防げることが特徴です。
コートf MD軟膏
-

- ウィークに分類されているプレドニゾロンが主成分の塗り薬です。炎症を抑えるグリチルレチン酸も配合されています。大人と比べて皮膚が未熟な赤ちゃんからでも使えることが特徴です。
亜鉛華軟膏
-
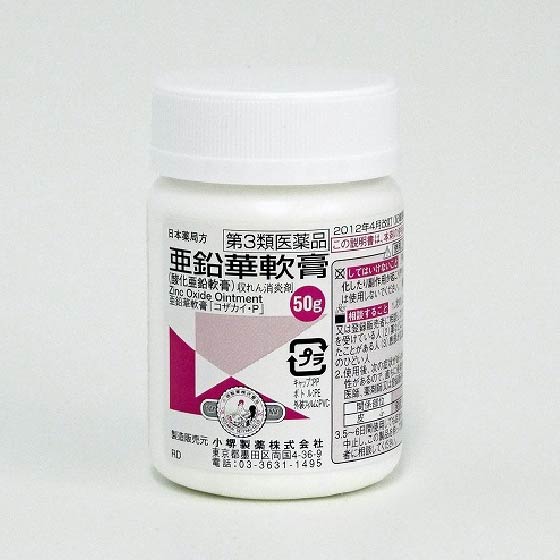
- 皮膚を保護し、じゅくじゅくを取り除く塗り薬です。0歳から使用できます。ステロイドと混ぜて使用しても問題ありません。
【漢方薬】アトピー性皮膚炎に使える市販薬
「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2021」でアトピー性皮膚炎に効果があるとされているのは、消風散と補中益気湯の2種類のみです。
消風散(しょうふうさん)
かゆみが強く、じゅくじゅくしている状態の改善に役立ちます。体力が中等度以上ある方向けです。ステロイド剤と併用することで症状の改善が見られたという報告があります。
補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
体力がなくて疲れやすく、胃腸の働きが落ちている方によく使われる漢方薬です。ステロイド剤と併用して服用することで、ステロイド剤の使用量を減らすことができたという報告があります。
アトピー性皮膚炎に関するQ&A
最後に、アトピー性皮膚炎に関してよく聞かれる質問に3つお答えします。
ステロイド剤は危ないと聞きましたが本当ですか?
適切に使用すればステロイド剤が危ないということは決してありません。自己判断で使うのを途中でやめてしまったり、塗る回数を減らしてしまったりすると症状のコントロールがうまくいかず悪化することがあります。
ステロイドを使わない民間療法でも治りますか?
民間療法のほとんどは科学的な効果が確認されていません。アトピーが悪化したり合併症が起こったりして入院した方の44%は民間療法を行っていたという報告もあります。
適切な治療を行うタイミングを逃すことにもつながるため、民間療法ではなく皮膚科で行われている標準治療を優先するようにしてください。
参考
アトピー性皮膚炎を予防する方法はありますか?
アトピー性皮膚炎の発症予防には、保湿が大事です。アトピー素因がある乳児にセラミドが配合された保湿剤を塗る試験を行ったところ、通常のスキンケアを行った乳児よりアトピー性皮膚炎の発症率が低かったという報告があります。
アトピー素因がない乳児に対しても有効なのかについてはまだわかっていませんが、セラミド配合の保湿剤でアトピー性皮膚炎の予防ができる可能性があります。
アトピー性皮膚炎が疑われるときは医療機関を受診しよう

アトピー性皮膚炎の治療は、皮膚科で行うことが基本です。薬を切らして一時的に市販薬を使うのであれば問題ありませんが、皮膚科の受診をせず市販薬から使い始めるのは避けてください。正しい治療を行うのが遅れると、症状の悪化につながります。
最近ではデュピクセントといって、重症のアトピー性皮膚炎にも有効な注射薬が登場しました。市販薬でできるアトピー性皮膚炎の治療は非常に限られていますので、早めに皮膚科を受診するよう心がけてください。
まとめ
アトピー性皮膚炎を市販薬で治療する場合は、塗り薬や漢方薬が候補となります。ステロイド剤は強さに応じて5段階にわけられており、このうち市販で扱いがあるのはウィーク、ミディアム、ストロングの3種類のみです。
処方薬のつなぎとして使う場合は、同じ強さの市販薬を選ぶようにしてください。アトピー性皮膚炎の治療は長期間にわたることがほとんどです。長期戦になるからこそ、医師に診てもらいながら治療を進めていくことが重要になります。
コラムニスト

薬剤師ライター 岡本 妃香里
薬剤師としてドラッグストアで働いていくなかで「このままではいけない」と日に日に強く思うようになっていきました。なぜなら「市販薬を正しく選べている方があまりに少なすぎる」と感じたからです。
「本当はもっと適した薬があるのに…」
「合う薬を選べれば、症状はきっと楽になるはずなのに…」
こんなことを思わずにはいられないくらい、CMやパッケージの印象だけで薬を選ばれている方がほとんどでした。
市販薬を買いに来られる方のなかには「病院に行くのが気まずいから市販薬で済ませたい」と思われている方もいるでしょう。かつての私もそうでした。親にも誰にも知られたくないから市販薬に頼る。でもどれを買ったらいいかわからない。
そんな方たちの助けになりたいと思い、WEBで情報を発信するようになりました。この症状にはどの市販薬がいいのか、どんな症状があったら病院に行くべきなのか、記事を通して少しでも参考にしていただけたら幸いです。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
 2024/05/02
2024/05/021つの市販薬なら問題なくても、複数の市販薬を同時に服用すると飲み合わせが悪い場合があります。とはいえ、「どれとどれを飲むとダメなの?」と疑問に思っている方が多いのではないでしょうか。
今回は、同時服用に注意が必要な市販薬の組み合わせについて紹介します。併用に気をつけたいサプリメントや処方薬、食品などについても解説しているので参考にご覧ください...続きを読む
-
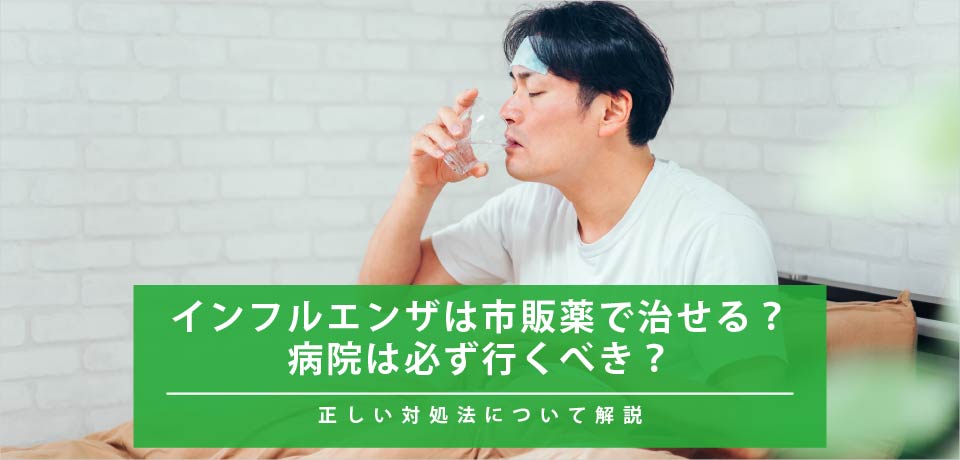 2022/11/11
2022/11/11冬になると流行しやすい感染症の一つがインフルエンザです。インフルエンザと思われる症状が出たとき、市販薬で対処してもよいのか、それとも病院に行くべきか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、症状の程度や重症化リスクの有無によっては市販薬でも対処できます。 しかし、インフルエンザの場合は使用できる市販薬に限りがあることに注意が必要で...続きを読む
-
 2025/01/10
2025/01/10水虫や陰部白癬、皮膚カンジダ症、脂漏性皮膚炎などの治療に用いられます。 医療機関で処方されたケトコナゾールを切らしてしまい、市販薬で対応したいと考えている方も...続きを読む
-
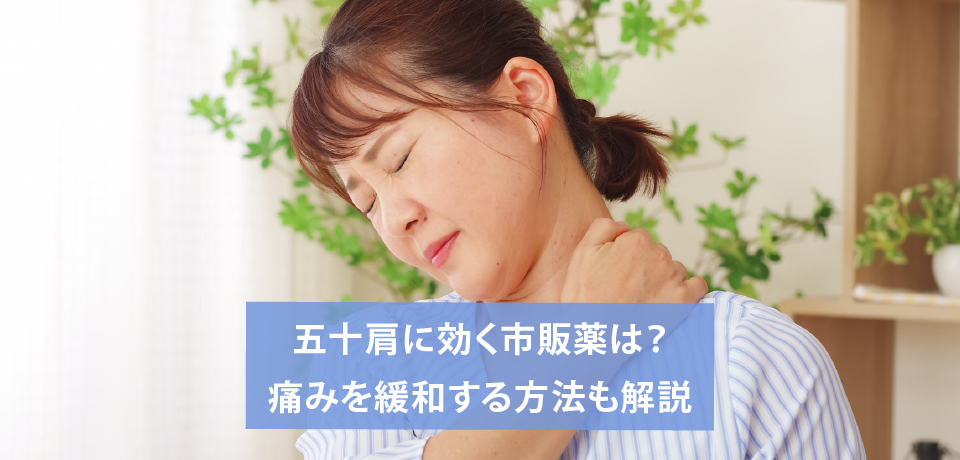 2024/11/27
2024/11/27「五十肩になってしまって腕を動かせない」 「電車のつり革につかまるのがつらい」
約20~50人に1人の割合で発症するといわれている五十肩は、生活に支障をきたすことから早期の治療が大切です。自然に治ることはあまりなく、放置しておくと症状が悪化...続きを読む




