
出産後、心身ともに不安定な状態の妻に対し、夫が今までと全く変わらず飲み会や自分の趣味を楽しんでいると、妻からの愛情がガクンと下がってしまう……。
当たり前といえば当たり前に思えますが、実はこの時期の愛情低下は「まったくもう!」で済むような一過性のものではなく、その後の夫婦関係に大きく影響し、老後までも左右する可能性があるといいます。
今回はそんな危機的状況を指す「産後クライシス」の意味や、なぜ起きるのか、夫婦で協力して産後クライシスを回避する方法などを紹介します。

産後クライシスの意味
「産後クライシス」のクライシスは「危機」という意味の英語で、2012年のNHKのテレビ番組ではじめて提唱され、使われるようになりました。
結婚して赤ちゃんが生まれるまでは夫婦がお互い愛し合っていたのに、なぜか出産後に妻から夫への愛情度が急激に下がってしまう現象のことをいいます。たしかに夫婦にとって危機的な状況ですよね。
きっかけはいくつかあるといわれています。
- 妻は肉体的にも生活リズムも大きく変化したのに、夫は全く変わらず過ごしている
- 夫が育児に参加せず妻任せ
- 妻にとって赤ちゃんの優先順位が夫より上になってしまった
- 妻のホルモンバランスの変化
そしてこれらはおたがいに関連し、悪循環を起こしていきます。
たとえば、産後まだダメージが大きい身体で育児をしている妻のことを夫が理解せず、今夜は赤ちゃんをお風呂に入れると約束したのに急に飲み会に出かけてしまう。
あるいは、夫が帰宅後もスマホに夢中で「おれは仕事で疲れてるから」と育児に参加しないでいると、妻は「赤ちゃんの命を守れるのは私だけ」と責任を感じ、赤ちゃんの優先度が夫よりも多くを占めるように。
そうしているうちに、お世話の仕方や赤ちゃんの喜ぶ遊び方など夫婦の「育児力」の差がどんどん開いていきます。
仕事は大切とはいえ、親になったのにまったく以前と変わらず育児を妻に任せきりの夫に対して「無性にイライラする」「前みたいに愛していると思えない」と妻の気持ちが変化するのはある意味当然かもしれません。
そして、低下した愛情がそのまま回復しないのが産後クライシスの要注意なところです。
厚生労働省の調査によると、同居期間20年以上の夫婦が離婚する割合は調査開始時(1950年)と比べて2020年には4倍以上に増えており、全離婚の5組に1組が熟年離婚という結果に。
産後クライシス後に愛情が回復しないままでは、将来の熟年離婚の可能性もより高まってしまうでしょう。
参考
産後クライシスが起きやすいのはいつからいつまで?
あるアンケート調査によると、結婚してまだ子どものいない夫婦のうち、「配偶者といると本当に愛していると実感する」と答えた人は男女ともに約75%だったそうです。
一方、赤ちゃん(0歳児)がいる夫婦に同じ質問をしたところ、夫は約65%が「そう思う」と答えたのに対し、妻は約45%と大きく減っています。
さらに2歳児のいる夫婦では、夫を「本当に愛している」と感じる妻は約35%、つまり3人に1人にまで減ってしまうそう。
その後は割合の変化は横ばいになることから、産後クライシスは、出産から子どもが2歳になるまでの時期に起きることがもっとも多いといえます。
参考
産後クライシスを夫婦で回避し、乗り越えるには

せっかく愛する人と結婚してかわいい子どもが生まれたのに、愛情度が大きく下がってしまうのはとても残念ですよね。
ぜひ産後の2年間には夫婦で協力して産後クライシスを回避したいもの。特に夫(パパ)のがんばりが期待されます。
2022年には育児・介護休業法が改正され、男性の育休は2回に分けて取得したり「産後パパ育休」として出産日に合わせて柔軟に取得したりできるようになりました。
育児休業取得率もまだまだ少ないとはいえ確実に増えてきており、育児に参加したいと思うパパの希望が少しずつ叶う世の中になりつつあります。
ただ、赤ちゃんのお世話や相手について学校や会社で学ぶことはほとんどないため、男女問わずはじめはみんな初心者です。
夜泣きの対応、ミルクをちゃんと飲んで体重が増えているのか、湿疹ができた、抱っこばかりで家事が進まないけどしばらく泣かせておいていいのか…こういった心配ごとは、日々赤ちゃんと接する中で少しずつ対処方法が分かってくるもの。
パパが育休を取れても取れなくても、家にいるときは関心を持って主体的に育児に関わり、分からないことは妻任せにせずに調べたり教えてもらったりする姿勢は、確実に産後クライシス回避に役立つでしょう。
ママもできるだけ育児の辛さや悩みを抱え込まずに、夫婦の間はもちろん外部の人にも助けを求め、ママ自身が幸せだと感じられる環境を遠慮せずに叶えていきましょう。
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
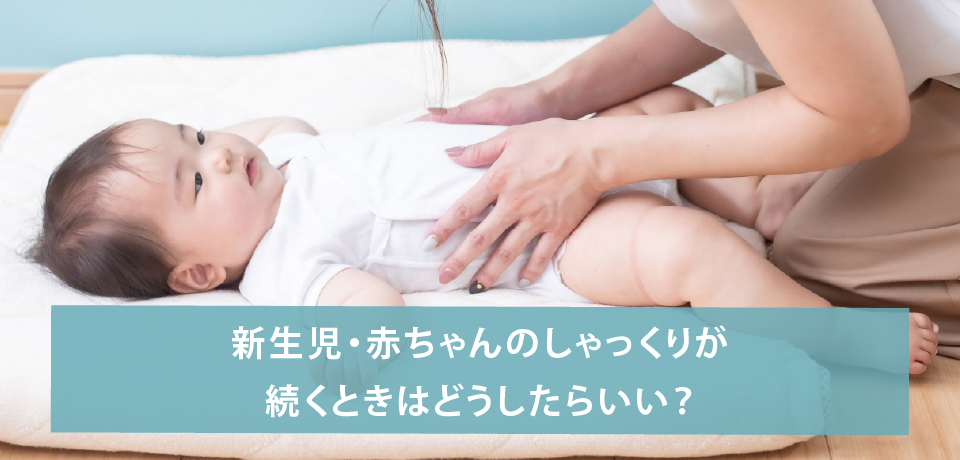 2024/09/24
2024/09/24赤ちゃんのしゃっくりがなかなか止まらず心配になったことはありませんか?
長いときには1時間ほど続くこともありますが、多くの場合、あまり心配はいらないと考えられています。 今回は、しゃっくりの原因や一般的な止め方、赤ちゃん向けの...続きを読む
-
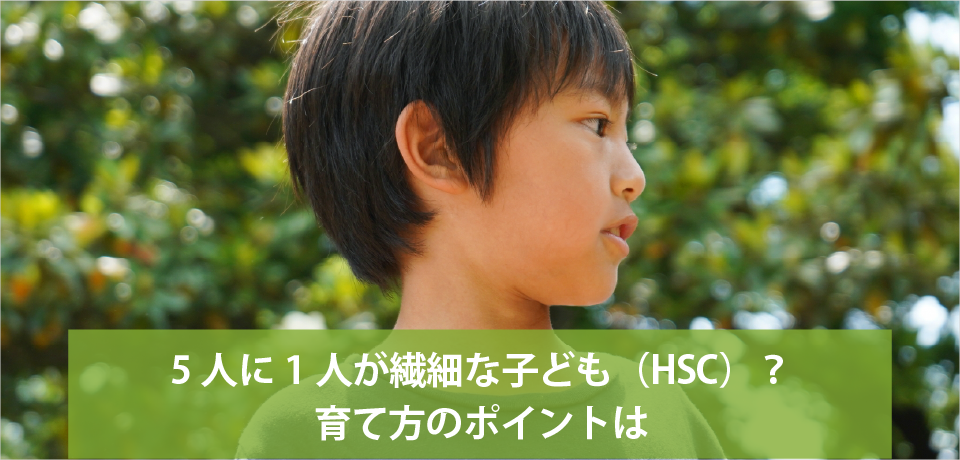 2023/12/07
2023/12/07もしかして、お子さんは、人口5人に1人の割合といわれる「HSC(Highly Sensitive Child)」かもしれません。 今回は、HSCの特徴や、...続きを読む
-
 2023/02/03
2023/02/03赤ちゃんが母乳やミルクを飲むのをやめ、食事での栄養に移行することを以前は「断乳」と呼んでいましたが、最近では赤ちゃんが自然に卒業するのを待つという意味合いで「卒乳」という呼び方も増えています。
この2つの違いや、タイミング、進め方について具体例をまじえて解説します。 赤ちゃんを育てていて「断乳と卒乳はどっちがいいの?向いているの?」と気になってい...続きを読む
-
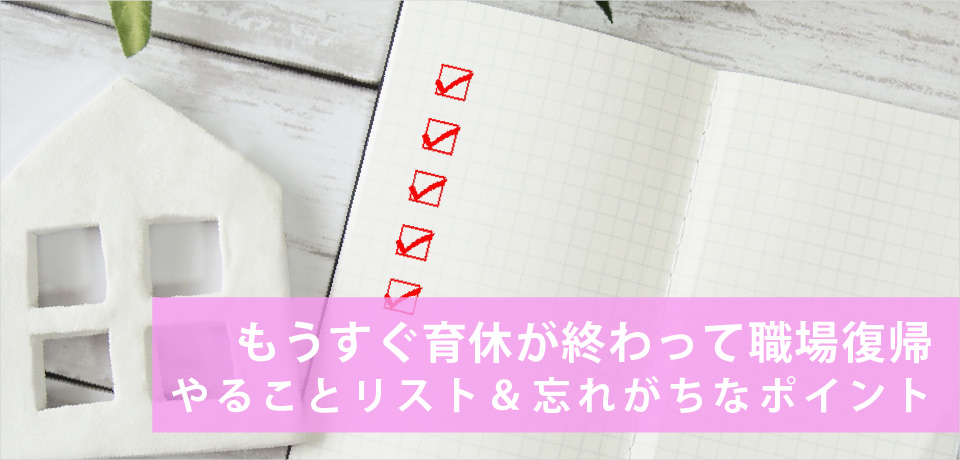 2022/03/14
2022/03/14昨年赤ちゃんを出産したママの中には、4月の入園のタイミングで育児休業を終えて職場復帰する人も多いと思います。
この何ヶ月のあいだ夢中で赤ちゃんのお世話をがんばってきて、さあ職場復帰!となると、「何を準備すればいいんだっけ…?」と戸惑っているママもいるのではないでしょうか...続きを読む




