
お子さんの体調不良時にお世話になる小児科の医院や病院。
成長にともない「そろそろ小児科じゃなく、内科に行くべき?」と考える人も多いと思います。
しかし具体的に何歳になったら小児科を卒業するべきなのか、はっきりした目安がなく迷っている方もいるのでは。
今回は小児科に通ってもよい年齢について取り上げます。
赤ちゃんは何歳から小児科に行けばいい?
妊娠中や出産時~退院までは、赤ちゃんはママと一緒に産院・産婦人科で身体のようすをみてもらいます。
その後は小児科に通うことになりますが、そのタイミングはいつからでしょうか?
この検診が終わった後からは小児科を受診するのが一般的です。赤ちゃんの成長につれてさまざまな病気にかかる機会が増え、産婦人科を受診すると妊婦さんや新生児に感染させてしまう恐れもあるためです。
小児科から内科に切り替えるタイミング

小児科を訪れる理由でもっとも多いのは発熱などの風邪症状かと思います。
小学生までは熱が出たら迷わず小児科を受診していたものの、中学生あたりから「そろそろ内科に行った方が良いのでは…?」と思い始める親御さんも多いでしょう。
ただ、この切り替えのタイミングは法律などで明確に定められていません。
厚生労働省の資料では、幼児や小児の年齢について以下のように定義しています。
①新生児とは、出生後4週未満の児とする。
②乳児とは、生後4週以上、1歳未満の児とする。
③幼児とは、1歳以上、7歳未満の児とする。
④小児とは、7歳以上、15歳未満の児とする。
上記にもとづいて考えると、小児科から内科に切り替えるタイミングは15歳、つまり中学校を卒業する時期となりますね。
しかし、日本小児科学会では平成18(2006)年に以下のような提言を行い、「成人するまで受診が可能」としています。
日本小児科学会では、小児科が診療する対象年齢を、現在の「中学生まで」から「成人するまで」に引き上げること、そして、その運動を全国的に展開することを、平成18年4月に決定しました。これまで小児科に通院していた15~20歳の方はもちろん、これまで小児科に通院していなかった15~20歳の方も、どうぞ、気軽に小児科医に御相談下さい。小児科医は、積極的に診察して参ります。
また平成30(2018)年に行われた、小児科卒業の目安を内科医と小児科医にたずねたアンケートでは、内科医の40%が「12歳」つまり小学校までと考えているのに対し、小児科医では50%が「15歳頃」と回答しており、小児科のほうが高い年齢まで受け入れる姿勢があることが分かります。
中学生・高校生でも小児科を受診する理由

「成人まで受診OK」と言われても、中学生・高校生のお子さんを小さな子がいっぱいの小児科へ連れていっても本当にいいのかな…とためらってしまう方もいるかもしれません。
中高生以上のお子さんがいるママ・パパに聞いてみたところ、小児科に通い続けていた理由には次のようなものがあったそうです。
- きょうだいが小学生や幼児で、一緒に診察や予防接種をしてもらえるから
- 喘息など慢性の持病があり、小さい頃から経過を知っている医師に診察してほしいから
- 地方在住で近くに内科がないから
- 一般に小児科の方が適しているといわれる疾患だから
- 生まれつきの特性で、慣れ親しんだ環境の方が安心して受診できるから
小児科の方が適しているといわれる疾患には、成長痛や起立性調節障害など、思春期特有のものがあげられます。
一方で中高生になって小児科にいくのをやめたケースでは以下のような理由がありました。
- 引っ越しを機に
- 内科が近所にあり、そちらの方が近いので
- 子供が恥ずかしがったので
- 中学校以降あまり体調を崩さなくなったのでどこにも通っていない
中高生で小児科に通う理由と内科に切り替える理由、それぞれ色々ありますが、お子さんの反応や通いやすさなどを総合的に考えて、最適な受診先を選んでいきたいですね。
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
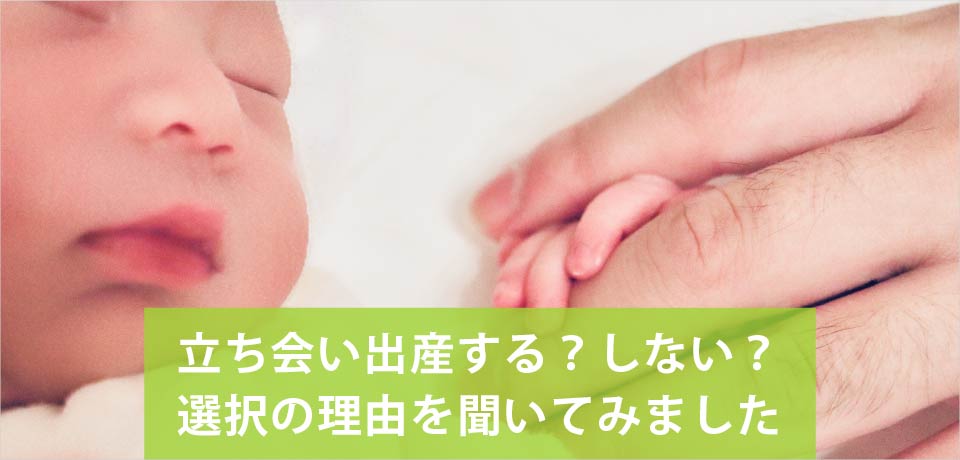 2022/02/14
2022/02/14コロナ禍で多くの産婦人科で中止されていた「立ち会い出産(夫立ち会い分娩)」ですが、感染対策をしっかり行った上で少しずつ再開されるようになってきました。
しかし、立ち会い出産をする・しないの判断は家庭ごとに異なり、夫婦お互いに考えや希望もありますよね。 今回は、経験者のアンケートをもとに、立ち会い出産する・...続きを読む
-
 2023/02/03
2023/02/03赤ちゃんが母乳やミルクを飲むのをやめ、食事での栄養に移行することを以前は「断乳」と呼んでいましたが、最近では赤ちゃんが自然に卒業するのを待つという意味合いで「卒乳」という呼び方も増えています。
この2つの違いや、タイミング、進め方について具体例をまじえて解説します。 赤ちゃんを育てていて「断乳と卒乳はどっちがいいの?向いているの?」と気になってい...続きを読む
-
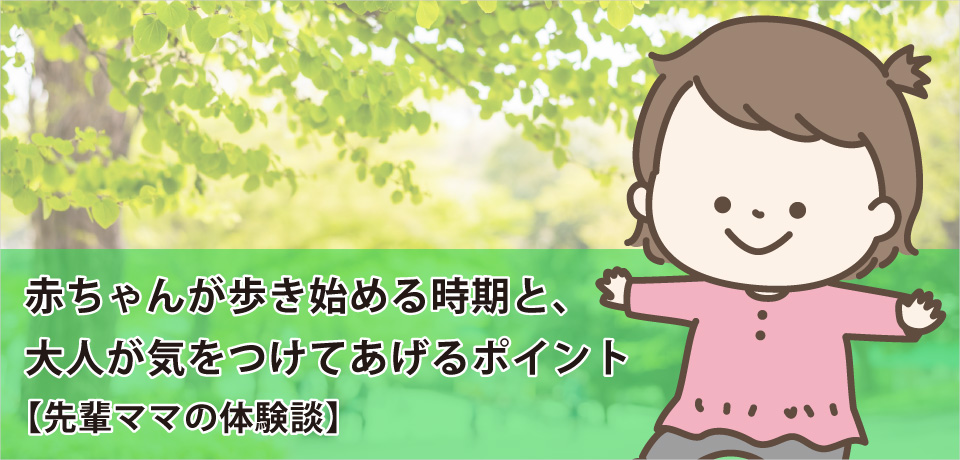 2021/05/24
2021/05/24赤ちゃんがハイハイからつかまり立ち、伝い歩きなどを始めたら、ママやパパは「もうすぐ歩くのかな!?」とドキドキワクワクしますね。
また「まわりの同い年の子は歩き始めているのに、うちの子はまだ…」と心配になっている人もいるかもしれません。 今回は、赤ちゃんが一般的に歩き始める時期と身体...続きを読む
-
 2022/12/19
2022/12/19赤ちゃんの生後6ヶ月をお祝いする「ハーフバースデー」って聞いたことありますか?
日に日に成長しめまぐるしい変化を見せる赤ちゃんの最初の1年だから、1歳を待たずに半年の時点で成長をお祝いするというものです。 今回は、ハーフバースデーの由...続きを読む




