
ハイハイや伝い歩きができるようになった赤ちゃんは、興味のある場所へ移動したり、家族の後を追いかけたりして、あちこち動き回るようになります。
「ベビーゲート」とは、部屋の出入り口や段差のある場所に取り付けて、赤ちゃんを危険から守る器具のこと。「ベビーフェンス」と呼ばれることもあります。
今回は、市販のベビーゲートの選び方や安全な使い方と、テレビ前などに置くだけで効果のある手作りベビーゲートのアイデアを紹介します。
市販のベビーゲートの選び方

ベビーゲートにはいくつかの種類があり、置きたい場所や目的によって使い分けるのがおすすめです。
幅や高さが調節できるタイプなら、引っ越したときや赤ちゃんの成長に合わせて長く使えるので便利ですね。
階段下や玄関
家の中でも、
- 階段の下(リビングが上階にあるお宅では階段上にも)
- 縁側や小上がりなど段差がある場所
- 屋外につながる玄関や勝手口
などは特にしっかりと対策したい場所。
赤ちゃんが力をかけても外れにくくおすすめなのは、壁や柱にネジなどで固定して取り付けるタイプのベビーゲート。少し成長した赤ちゃんや幼児も乗りこえられない、高さ100cm前後のものが安心です。
賃貸住宅や金属サッシ等でネジ穴を空けられない場合は、突っ張りタイプを選びましょう。
ただし、突っ張り強度によっては「階段上には使用できません」という製品もあるので、購入する時にはよく確認してくださいね。
キッチン
包丁やガスコンロなど危険なものが多いキッチン。調理中は特に赤ちゃんが入れないようにしておきたいですよね。
ただ、調理の途中で赤ちゃんのお世話をしてまたキッチンに戻って調理の続き…を繰り返すことも多いため、大人がさっとまたいで移動できる高さ60cm程度のベビーゲートや、閉めると自動的にロックがかかる扉付きタイプなどが行き来しやすく便利です。
ただし、またぎ越すタイプのベビーゲートは大人でも足をひっかけて転ぶ危険性があるため、熱いものを手に持ったり、赤ちゃんを抱っこしたままでまたぐのは絶対に避けましょう。
部屋の仕切り
上のお子さんが宿題やお絵かきをしたり、小さなパーツのあるおもちゃで遊んだりするときは、赤ちゃんの安全を守りつつ上の子の邪魔をしないように、仕切りとしてベビーガードを置くのもよいですね。
同じくペットとの仕切りとしてベビーゲートやベビーサークルを置いているご家庭もよく見かけます。
このような場合は手軽に移動できる「自立タイプ」のベビーゲートや、角度調節できるもの、連結できるものなどが扱いやすくておすすめです。
テレビ前などに。手作りベビーゲートのアイデアと注意点

ベビーゲートは、階段や玄関など転落の危険性がある場所には必ず安全基準をクリアした市販品を使用したいですが、価格も1台で数千円~数万円するため、いくつも購入すると費用もかさんでしまいます。
ゲートがないと危険とまではいかないものの、赤ちゃんには少し離れていてほしい……という場所では、手作りのベビーゲートで対処しているママも。
注意点としては、倒れたりつぶれたりしないよう、少なくとも奥行き3本以上を並べてしっかりした枠組みを作ることだそう。
同じように牛乳パックで作った手作りベビーゲートをこんなふうに使っているというママも。
Yさん・生後7ヶ月の男の子のママ
Tさん・4歳と1歳の女の子のママ
このように転落などの危険がない場所で、短期間しか使わないことが分かっている場合、手作りのベビーガードで乗り切る方法もあります。
赤ちゃんの安全を守りつつ、ハイハイやヨチヨチ歩きのかわいい時期を親子で楽しく過ごして下さいね。
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
 2022/02/16
2022/02/163月3日の桃の節句ももうすぐ。わが子の健康や幸せを祈って「雛人形」を飾る家庭も多いと思います。
ですが「雛人形っていつ出せばいいの?」と疑問に思っているママ・パパもいるのではないでしょうか。 今回は雛人形を飾る日としまう日、姉妹にはそれぞれ雛人形を買...続きを読む
-
 2021/04/05
2021/04/05赤ちゃんや小さな子どもは本当にかわいいですが、言葉を話せないがゆえの苦労もありますよね。
その中でもママやパパを困らせることの1つが、なんにでもイヤと答えたり、気に入らないことがあるとかんしゃくを起して大泣きしたりする、いわゆる「イヤイヤ期」ではない...続きを読む
-
 2024/08/19
2024/08/19赤ちゃんの離乳食や2歳頃までの幼児食には、基本的には唐辛子やワサビなどの辛い調味料は使いませんよね。
その後、3歳・4歳と成長するにつれ、だんだん大人と同じ食事に近付いていきますが、辛い味付けはいつ頃から、どの程度なら食べられるようになるのでしょうか? 実...続きを読む
-
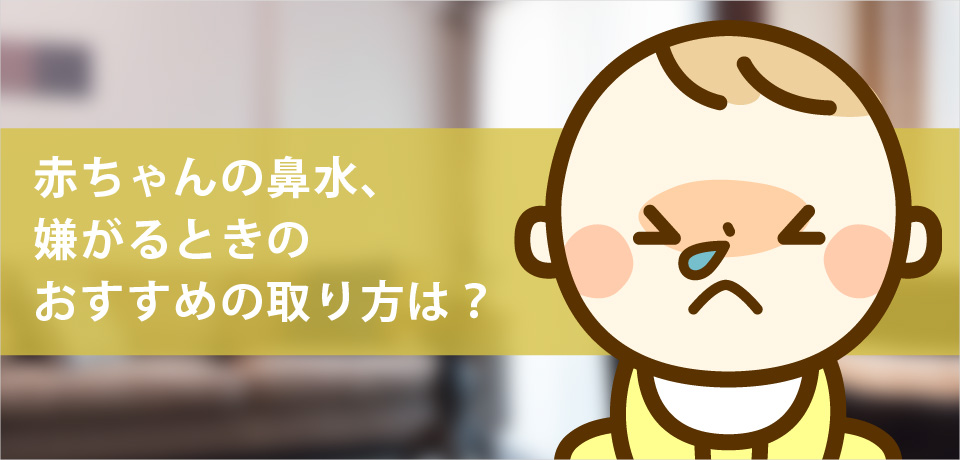 2022/01/19
2022/01/19寒い季節、赤ちゃんが風邪などで鼻水が出たり鼻が詰まったりすると苦しそうですよね。でも拭いたり吸ったりしようとするとたいてい嫌がります。
なにかいい方法はあるのでしょうか? 今回はママ・パパたちの体験談も参考に、じょうずに赤ちゃんの鼻水を取ってあげるコツを紹介します。 赤ちゃんは鼻水が出や...続きを読む




