
新しいおもちゃを買ったばかりなのに、夢中で遊ぶのはほんの少しの間で、すぐ飽きてしまう…。
と思ってしまいますよね。
今回は、子供がすぐおもちゃに飽きてしまう理由と、飽きずに長く遊べるおもちゃの選び方・使い方のコツを解説します。
すぐにおもちゃに飽きてしまう理由とは
まずは、子供の発達や心理から、すぐにおもちゃに飽きてしまうのはなぜか考えてみました。
子供の集中力は「年齢+1分」とも
子供が小さい間はできるだけ一緒に遊んであげたいものの、食事の支度や後片付けなど手が離せない家事の間は、おもちゃで1人きげんよく遊んでくれると助かりますよね。
誕生日やクリスマスなどで新しいおもちゃを買ったばかりだから喜んで遊ぶはず…なのに、5分もたたないうちに「ママー来てー」ということも多いのではないでしょうか。
実は、子供の集中力というのは大人と比べて短く、年齢+1分という説もあるほど。
なかにはじっくりと1つのおもちゃで遊ぶ子もいますが、それはその子の個性であって、基本的には「すぐ飽きる」のが当たり前と考えておいた方が良さそうです。
なお、動画やアニメはもう少し長く見ている子も多いですが、それらは制作のプロによって、子供の注意を惹きつけるよう画像や音を計算して作られているからです。身近なおもちゃの何倍もの刺激があり、どんどん画面が変わるため、長く見続けてしまうのですね。
対象年齢が合ってない

プレゼントやお下がりでいただいたおもちゃにあまり反応しない時は、対象年齢に合っていない可能性もあります。
まだ早すぎる場合は、赤ちゃんであれば誤飲などの心配もあるので一旦しまっておきましょう。対象年齢になって出した時には喜んで遊ぶかもしれません。
遊び方を限定しすぎ
決まった遊び方があるおもちゃを初めて使うとき、赤ちゃんや子供が自分流に使おうとすると「違う違う、それはこうだよ」と教えたくなりますよね。
しかし、たとえ説明書どおりの遊び方ではなかったとしても、逐一「ここに入れて」「こうだよ」と指図すると、言われたことをこなすだけになり飽きてしまう可能性も。
たとえば線路を逆につないでしまい思い通りに電車が走らないとか、小さい積み木の上に大きい積み木を重ねたせいで崩れてしまうなど、大人から見ると当たり前の失敗も、子供にとっては何回も繰り返して自分で気付くのも大切なプロセスだからです。
まずは様子を見て遊ばせてあげた上で、うまく行かずに興味を失ってしまう前に「こうしてみたら?」とヒントを出すくらいが適切な関わり方だといえます。
飽きないおもちゃの選び方
年齢性別の異なるきょうだいがいるとおもちゃの数はさらに増えてしまいがち。収納スペースには限りがあるので、できれば飽きずに長く遊べるおもちゃを厳選して揃えたいですよね。
小さくてもその子によって好みがあり「これなら絶対飽きない」というおもちゃはなかなか存在しませんが、一般的に長く遊べるおもちゃには次のような特徴があるといわれています。
- 自分でやってみたらうまくいった!という成功体験ができる
- 気に入ったらパーツを買い足せるなど、拡張性がある
- いろんなものに見立てる・他のおもちゃの補助として使えるなど応用が効く
たとえばブロック類であれば、組み立てて遊ぶ以外にも、並べてドミノ倒しをしたり、お人形の家や乗り物を作ってみたりと幅広く遊べますね。
使いやすい工夫で、さらに長く遊べる

最後に、子育て中のママ・パパが実際にやっているおもちゃで長く遊ぶための工夫もいくつか紹介します。
Uさん・3歳の男の子のママ
Mさん・2歳の女の子のママ
Yさん・4歳の男の子のママ
などなど、工夫しだいで「すぐ飽きちゃう……」が回避できるかもしれません。
しかし、やはりおもちゃを与えるだけで1人で長く遊べる子は少数派。
そもそも子供は飽きっぽいということを念頭に、どんな遊び方が好きなのかを一緒に遊びながら見つけていってあげたいですね。
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
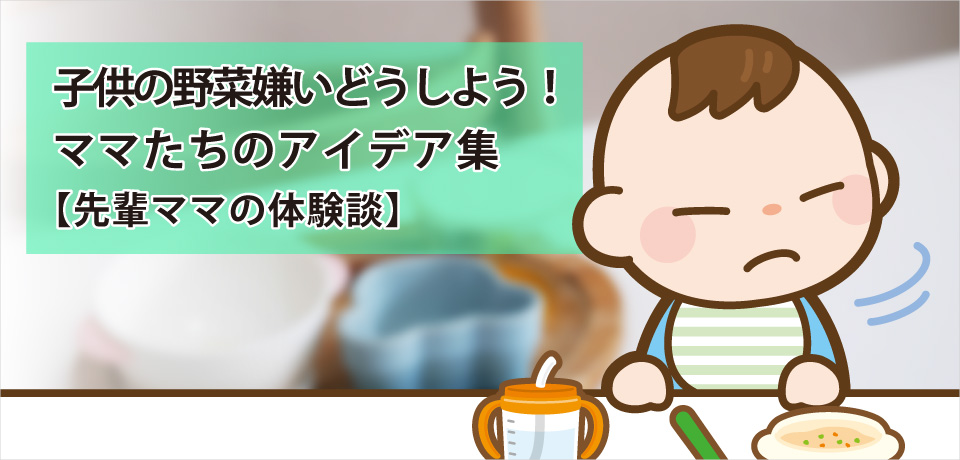 2021/06/21
2021/06/21育児の困りごとは様々ですが、なかでも「食」にまつわる悩みは毎日のことだけに大変ですよね。
食が細い、好みが偏っている…なかでもわが子の「野菜嫌い」で悩んでいる親御さんは多いのではないでしょうか。 そこで今回は、赤ちゃんの離乳食から小学生まで、先...続きを読む
-
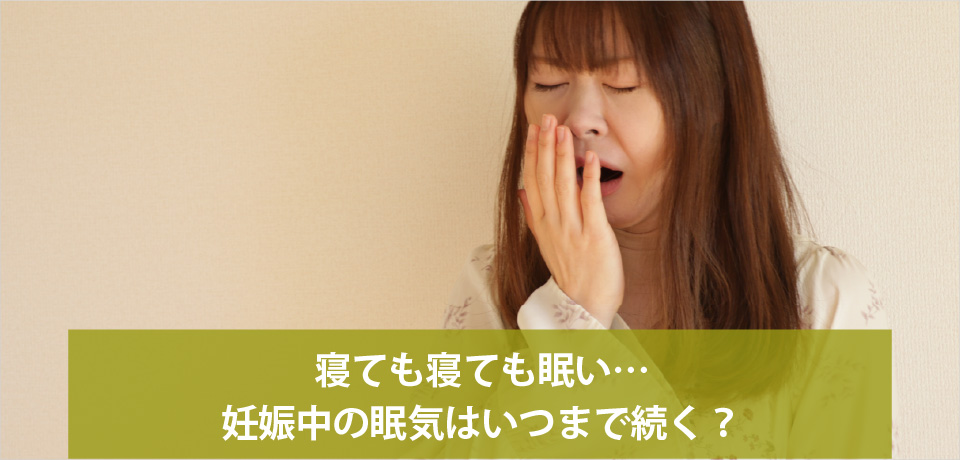 2023/10/11
2023/10/11妊娠中は「とにかく眠くて眠くてたまらない」という人は多いもの。
理由としては、ホルモンバランスの変化や、できるだけ安静にして妊娠初期の赤ちゃんを守る身体の仕組みだという説もありますが、寝ても寝ても眠い状態が長く続くと、会社で...続きを読む
-
 2023/04/24
2023/04/24この春お子さんが小学校に入学したご家庭の皆様、ご入学おめでとうございます!
小学校では初めての体験がいっぱいですが、朝、近所の子供たちが公園などに集合してみんなで学校に行く「集団登校」もそのひとつですよね。 「慣れるまでのあい...続きを読む
-
 2021/11/24
2021/11/24公園の砂場や自宅で子供たちが遊んでいるとき、おもちゃの貸し借りでケンカになることがありますよね。
「どうしたらスムーズに貸して・いいよができるの?」 「他の子はできるのにウチの子はなかなかおもちゃが貸せない…」 といった悩みに対し、年齢別のおすす...続きを読む




