
初めての赤ちゃんが生まれたり引っ越しで環境が変わったりした際に、体調不良時にすぐ相談できる「かかりつけ医」を決めておかなくては……と思いつつ、見つけ方や選び方が分からないというママ・パパはいないでしょうか。
今回は、赤ちゃんや子供の「かかりつけ医」の決め方のポイントについて解説します。
かかりつけ医とは

これを読んでいる大人の皆さんは、熱が出たら内科・肌のトラブルは皮膚科・腰痛は整形外科など、個別に受診している人も多いかと思います。
しかし昔はどこの家にも、地域のお医者さんが家族の病気をみてくれる「かかりつけ医」がいて、まずはその先生の見立てによって治療したり、必要に応じて大きい病院や専門医を訪れたりしていました。
近年は大きな総合病院に受診が集中し、本来そこで治療が必要な患者さんへの対応が難しくなるという問題がありました。そこで始まったのが「かかりつけ医」制度です。
かかりつけ医の定義は以下のように言われています。
参考
ちょっとわかりにくいかもしれませんが「身近で通いやすい場所に信頼できるお医者さんがいて、自分の健康状態や持病・特有の事情などを知っておいてもらえると安心」という考え方ですね。
かかりつけ医の見つけ方

「かかりつけ医をもとう」と言っても、通常の体調不良や病気をみてもらうために何か登録や申し込みが必要というわけではありません(※介護や福祉に関わる地域包括ケアシステムの利用に際してはかかりつけ医を指定することがあります)。
また、できる限り同じ医院や医師にすべてカバーしてもらえるのが理想的ですが、さまざまな事情で難しい場合は分散しても構いません。
なにかあったときに相談できて信頼できるお医者さんならここ…と思い浮かべることができればOKです。
かかりつけ医を探すための支援を行っている自治体では、病院の待合室の冊子や自治体のホームページに医院の一覧や特徴が紹介されていることもあります。
アメリカやイギリスでは家族で「かかりつけ医」を決める制度が日本よりも浸透しています。「かかりつけ医」は英語で『Family doctor』となっており、このサイト『Family doctor(ファミリードクター)』はその英語の「かかりつけ医(Family doctor)」が由来の一つです。
ファミリードクターのサイト内では地元広島の病院やクリニックを、現在地の距離や診療科や地域などで検索できます。
また「Pick Up!ドクター」のコーナーでは、広島で活躍するドクターに、実績や治療に対する取り組み・思いをインタビューしていますので、広島にお住まいの方はぜひかかりつけ医を見つける参考にして下さいね。
赤ちゃん・子供のかかりつけ医を決めるポイント
初めての赤ちゃんを迎えたママ・パパや、新しい土地に引っ越したときは、体調不良時にみてもらえる小児科を早めに探しておきたいですよね。
まずは、通える範囲の小児科やクリニックをピックアップし、以下のような点を比較しながら選んでいきましょう。
場所やアクセス
赤ちゃんや子供の体調不調時にできるだけ早く受診できるよう、自宅や保育園・学校から近い場所、自家用車なら駐車場があるところ、公共交通機関なら駅やバス停から近いところがおすすめです。
診察時間・予約
赤ちゃんや小さい子はふいに熱を出したり体調を崩すことも多いものですが、大きい総合病院では外来受診は午前中だけということがほとんど。午後や夜など診察時間が広い医院やクリニックが安心です。
また「急を要するほどではないけれど診てもらいたい」という場合、予約制の医院やクリニックであれば、何時間も待合室で具合の悪い子供と待たなくて済みます。
院内の環境
インフルエンザや新型コロナはもちろん、子供特有の水ぼうそうなど感染しやすい病気の予防として、待合室を分けたり、空気清浄機を置いたり、換気や清掃の行き届いた小児科なら安心ですね。
またベビーベッドやおむつ替えスペースがあると赤ちゃんにも安心ですし、プレイコーナー・おもちゃや絵本などがあると少し大きいお子さんも待ち時間を退屈せず過ごせます。
ドクターとの相性
お医者さんとの相性が良いとさらに良いですね。小児科のドクターは児童心理なども学んでいますが、「物静かでていねいな先生」「元気で明るい先生」などお子さんやママ・パパと合うタイプの先生ならベストです。
クチコミや評判
初めてのお子さんや、引っ越したばかりのときは、「あそこの小児科どうかな?」と思ってもなかなか様子がわからないですよね。
公園や支援センターで出会うママ友や、近所の人に聞いてみると「A医院はおじいちゃん先生で診察はゆっくりだけどやさしいよ。テキパキした先生がよければB医院」「Cクリニックは院内処方だから、赤ちゃん連れで薬局を回らなくてもよくて助かる」などリアルな評判がわかります。
もちろん、ファミリードクターのような、インターネットのクチコミサイトもぜひ参考にして下さいね!
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
 2021/09/10
2021/09/10赤ちゃんのふわふわの髪はとっても可愛いですよね。しかし、早い子では1歳前後から髪が伸びてきて「そろそろヘアカットしなきゃ」と考えはじめる親御さんもいるかと思います。
今回は子供のヘアカット・散髪について、アンケート結果も参考に、サロンの選び方や美容院デビューの時期などを紹介していきたいと思います。 また、自宅で散髪に挑...続きを読む
-
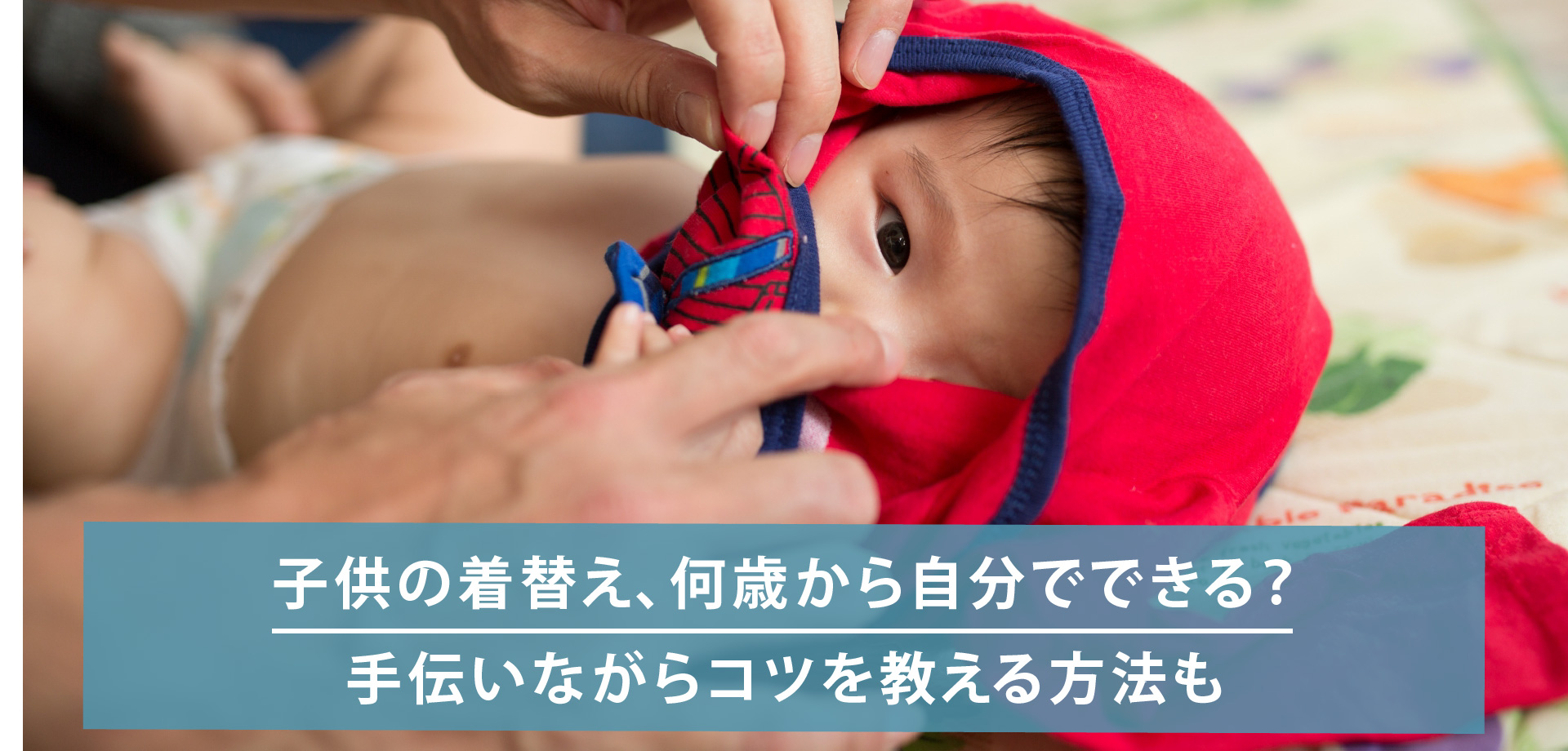 2024/07/03
2024/07/03保育園や幼稚園への朝の登園準備やお風呂上がりなど、子どもの着替えは欠かせないお世話のひとつ。
「時間に追われていつも親が着替えさせているけど、いつごろから1人でできるようになるのかな?」 「最近、自分で着替えたがるけど、なかなかうまくで...続きを読む
-
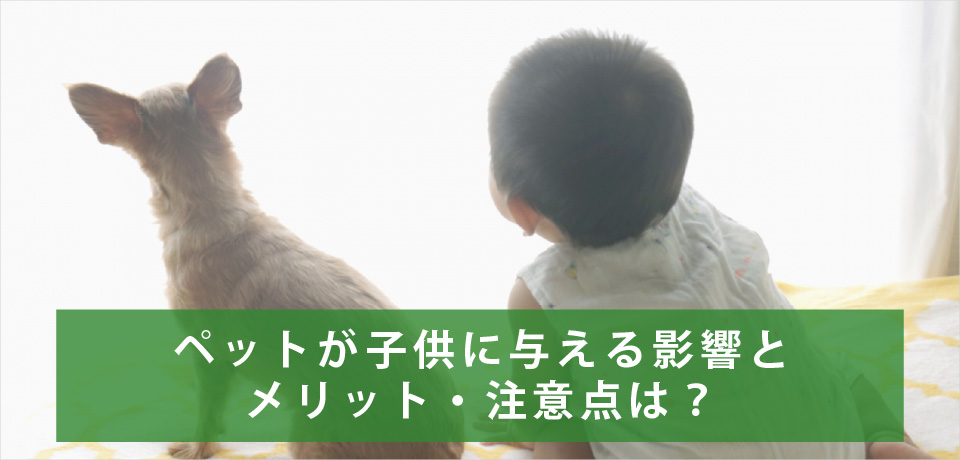 2023/04/19
2023/04/19皆さんの中に、ペットと暮らしながら子育てしているお宅はどのくらいいらっしゃるでしょうか。
ペットはいないという家庭でも、お子さんが3~4歳から小学校低学年くらいになると、お友達の家や絵本・アニメなどの影響で「ワンちゃんを飼いたい」と言い出したり、ショ...続きを読む
-
 2024/09/30
2024/09/30小さい子が大好きな「ごっこ遊び」。お家で毎日のようにお店屋さんやお医者さんなど「〇〇ごっこ」をやりたがるお子さんにつきあうのが大変…というママやパパもいるかもしれません。
でも実は、子どもの成長や発達に「ごっこ遊び」は重要な役割を果たしているんです。今回はその理由を解説します。 なぜ小さい子は「ごっこ遊び」をしたがるの? ...続きを読む




